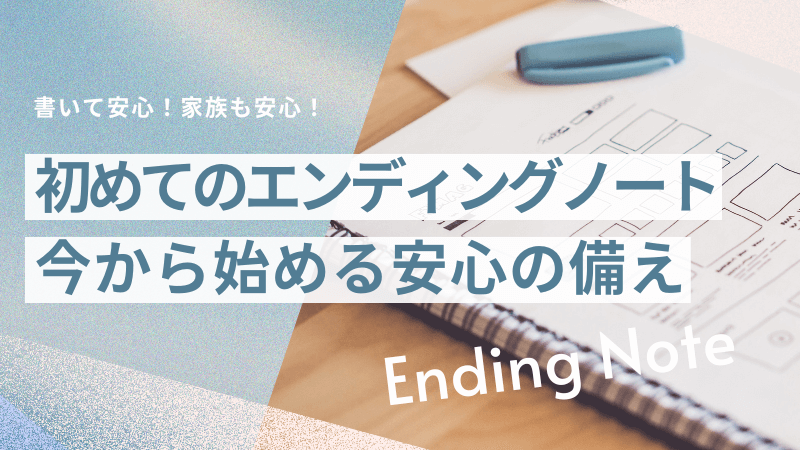「エンディングノート」とは、ご自身の人生の終わりに向けて、残しておきたい情報や思いを記しておくノートのことです。万一自分が病気や事故で意思を伝えられなくなったとき、あるいは亡くなった後に、家族に伝えたいことをまとめておくためのものです。エンディングノートには決まった書式はなく、自由に書けるのが特徴です。遺言書のような法的文書ではありませんが、その分形式にとらわれず、自分の希望や大切な情報を幅広く残しておけます。主な目的は「自分のための備忘録」であると同時に「家族へのメッセージ」でもあり、終活(人生の終わりの準備)の一環として注目されています。
目次
エンディングノートはなぜ必要?本人と家族へのメリット

エンディングノートを作成する最大のメリットは、残された家族の負担を軽減できることです。いざというときに備えて情報を整理し備えておくことで、万一のときに家族が何をすればよいかが明確になり、混乱や手間が減ります。たとえば金融機関の口座や保険の情報がまとまっていれば、相続手続きがスムーズになり、葬儀の希望が書かれていれば遺族は迷わずに準備を進められます。
また本人にとっても、人生を見つめ直す機会になり得ます。自分史やこれまでの歩みを振り返り、家族や友人への感謝の気持ちを書き記すことで、心が整理され前向きな気持ちになる方もいます。書き終えた後は「これで一安心」と心の荷物が軽くなるでしょう。実際、エンディングノートを準備している人からは「母親が倒れた際に、きちんと終活していて大変役に立った」「自分が死んだ後、残された家族が色々な手続きに困らないようにするため」という声が上がっています。このように家族への思いやりと自分の安心感の両方を得られる点で、エンディングノートはとても有意義なものなのです。
エンディングノートに何を書く?具体的な項目例
エンディングノートには決まりはありませんが、一般的に次のような4つのカテゴリーに沿って情報を整理すると分かりやすいでしょう。
自分自身に関すること
氏名や生年月日などの基本情報、マイナンバー、健康保険証番号、連絡先一覧(親族・友人の電話番号や住所)など。特に連絡先は、万一の際に誰に連絡すべきか家族が把握できるように書いておきます。また、学歴・職歴や趣味、思い出話など、自分の歩みを振り返る内容を含める方もいます。これらは形式ばらずに、自由に書いて構いません。あなたの人となりが伝わる記録にもなり、家族が読んだときに新たな発見や思い出を共有できるでしょう。
財産・資産に関すること
預貯金の口座情報(銀行名、支店名)、株式や債券などの金融資産、生命保険(保険会社名や契約内容)、年金に関する情報、不動産の所有状況、借入金やローンなどをリストアップします。通帳や印鑑の保管場所も書いておくと親切です。特に負債(借金)がある場合は、その額や返済方法、連帯保証人の有無まで記しておくと、残された家族が対処しやすくなります。クレジットカードや携帯電話、各種公共料金の支払い情報、インターネットのID・パスワードなども忘れずに(※パスワード自体は直接書かず、ヒントや別保管を推奨)。資産情報は定期的に見直し、最新の状態に更新しておきましょう。
医療・介護の希望
自分が病気になったり介護が必要になったりした場合に備えて、希望する医療や介護の内容を書いておきます。たとえば、延命治療をどこまで望むか、尊厳死の意思、認知症になった場合の対応、介護をお願いしたい人や施設の希望などです。事前に家族と話し合っておくことが大切ですが、ノートにも改めて「もしものときは○○してほしい」という形で意思を残しておくと安心です。また、かかりつけ医や持病・常用薬、アレルギーなどの医療情報、介護保険証の番号、臓器提供の意思表示などもこの欄に記載できます。
葬儀・お墓と相続の希望
葬儀の方法や規模、宗教・宗派、連絡してほしい人(または呼ばなくてよい人)のリスト、遺影に使ってほしい写真の指定、埋葬方法やお墓の場所など、葬儀と供養に関する希望を書いておきます。生前に伝えにくいことですが、ノートに残しておけば家族も故人の希望に沿った送り方ができるでしょう。また、遺言書の有無や保管場所もここで明記します。エンディングノート自体に遺産の分け方を書いても法的効力はありませんが、遺言書がある場合は「〇〇に保管」「弁護士△△先生に依頼済み」など詳細を書いておくと、いざというとき家族が探し出しやすくなります。遺言書を作成していない場合も、「遺言書は未作成です」と一言書いておくだけで、家族が戸惑わずに済むでしょう。
※このほか、ペットを飼っている方はペットの引き取り先や世話の仕方も記しておく、家族や友人への感謝のメッセージを書く、自分史や思い出深い出来事を書き留めておく、今後やりたいことリストを書く、といった項目を設けることもできます。エンディングノートは自由度が高いので、自分と家族にとって役立ちそうな内容を好きなだけ盛り込んで構いません。
エンディングノート作成のコツと注意点

1. 書きやすいところから始める
いきなり全ての項目を埋めようとしなくても大丈夫です。まずは名前や住所など基本情報から書き始めてみましょう。思いつくところ、書けるところだけでも少しずつ埋めていけばOKです。一度に完璧に仕上げる必要はありません。思い立ったときに書き足し、後から何度でも修正できるのがエンディングノートの良いところです。
2. 続けやすい工夫をする
書きっぱなしにせず、節目ごとに見直す習慣をつけましょう。例えば毎年のお誕生日やお正月、結婚記念日など、「年に一度書き換える日」を自分で決めておくと更新を忘れにくくなります。定期的に見返すことで内容の古い部分に気づき、常に最新の情報にアップデートできます。
3. テンプレートや市販のノートを活用する
白紙から書こうとすると大変ですが、今は市販のエンディングノート(終活ノート)や無料ダウンロードできる様式もあります。項目立てがあらかじめ用意されているので、質問に答えるように書き込むだけで必要な情報を漏れなく整理できます。文房具店や書店で専用ノートを買ってもいいですし、手持ちのノートやパソコンで自作しても構いません。ご自身が書きやすい形式を選びましょう。
4. デリケートな情報の扱いに注意
エンディングノートには金融資産やパスワードなど重要な情報も書くため、取扱いに注意が必要です。第三者の悪用を防ぐため、銀行の暗証番号やオンラインサービスのパスワードそのものは直接書かない方が無難です(どうしても記す場合は暗号化したメモやヒントを書くにとどめ、別紙に詳細を書いて厳重に保管する方法もあります)。また個人情報のかたまりですので、保管場所も考えましょう。しまい込みすぎないこともポイントです。せっかく書いても家族が存在に気づかなければ意味がありません。かと言って誰でも目にする場所に置いておくのも考えものなので、信頼できる家族に預けたり、自宅の分かりやすい場所に保管したりといった工夫をしてください。
5. 遺言書ではないことを理解する
繰り返しになりますが、エンディングノート自体に法的な効力はありません。財産の分け方などについて「希望」を書くことはできますが、それはあくまで家族へのお願い・メッセージであり、強制力はないのです。財産の正式な分配をしたい場合は、公正証書遺言など法律にのっとった遺言書を作成する必要があります。そのため、エンディングノートを書いていて「ここは絶対に法的に遺したい」という事項が出てきたら、専門家に相談して遺言書の準備も検討しましょう。ただしエンディングノートには遺言書の有無や所在を書いておくことで、遺言書とセットでより有効に機能します。エンディングノートと遺言書、それぞれの役割を理解して賢く活用しましょう。
エンディングノートはいつから、どう始める?
エンディングノートを書き始めるのに「早すぎる」ということはありません。興味を持ったそのときが始めどきです。「まだ元気だから先でいい」と後回しにしがちですが、元気なうちに用意しておく方が内容もしっかり充実させられますし、万一の事態にも間に合います。実際、専門家の中には 「エンディングノート作成は20~30代で始めるのがおすすめ」 という人もいます。それほど早い時期から始めても良いくらいですが、70代・80代の方でも遅すぎることはありません。「思い立ったが吉日」で、今日からでも少しずつ書き始めてみましょう。
始め方のステップとして、まず家族に「エンディングノートを作ってみようと思う」と話してみるのも良いでしょう。突然ノートを書き始めると驚かれるかもしれませんが、「自分のための整理だから」と伝えればご家族も安心して協力してくれるはずです。その上で、先述のような市販ノートを購入するか、手持ちのノートを一冊用意します。表紙に「エンディングノート」とタイトルを書いておくと後で見つけやすいでしょう。書き出しは先ほどのコツにもあったように、書きやすい項目からで構いません。例えば住所や連絡先を書くだけでも立派な第一歩です。自分のペースで無理なく始めてみてください。
エンディングノートを家族と共有する方法とタイミング

エンディングノートは作成して終わりではなく、家族と適切に共有してこそ意味があるものです。せっかく書いても、誰にも知られず遺品の中から発見されるようでは有効に活かせない場合があります。理想的には、ノートを書いたこと自体は家族に知らせておき、必要なときに見てもらえるようにしておくのが望ましいです。
共有のタイミングとしては、大きく二通り考えられます。ひとつは「生前に内容を見せて共有する」方法、もうひとつは「ノートの存在と場所だけ伝えておき、内容は万一のときに開いてもらう」方法です。どちらが正解ということはありませんが、ご自身の考えに合う方を選びましょう。
生前に共有する場合
家族と一緒にエンディングノートを作成してみるのも良い体験です。例えば配偶者や子供と「どんなことを書こうか」と話し合いながら項目を埋めていけば、家族も内容を把握できますし、書く方も安心感があります。特に介護や医療の希望、葬儀の希望などは事前に家族へ伝えておいた方がよい事項です。エンディングノートを書き終えたり区切りの良いところまで書けたら、一度家族に読んでもらい、意見や質問を受け付けるのもいいでしょう。家族が内容を知っていれば、もしものときすぐにノートを参照して対応できます。
ノートの所在だけ伝える場合
中には「内容を見られるのは少し恥ずかしい」「生前に知られると落ち着かない」という方もいるかもしれません。その場合は、ノートをどこに保管したかだけ信頼できる家族に伝えておき、「自分に何かあったときにこのノートを開いて」とお願いしておく方法もあります。例えば「机の引き出しにエンディングノートが入っているから、何かあったら見てね」と一言伝えておけば安心です。実際に開封してもらうのは万が一のときだけ、と決めておけばプライバシーも守られます。
いずれにせよ、家族に存在を知らせておくことだけは忘れないようにしましょう。また定期的に更新している場合は、その旨も伝えておくと良いです(「毎年誕生日に書き換えているよ」など)。最新の内容が反映されたノートを使ってもらえるよう、アップデート後には家族に一声かけておく気遣いも大切です。
エンディングノートの法的効力と遺言書との違い
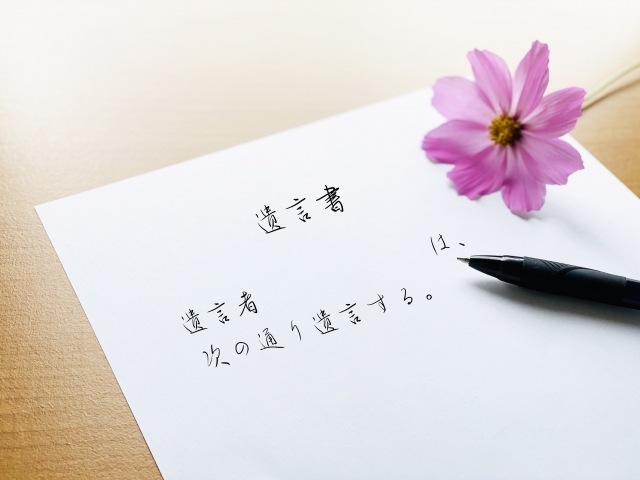
エンディングノートと遺言書は目的や役割が一部似ていますが、決定的に違うのは法的な効力があるかどうかです。遺言書(は民法で形式や要件が細かく定められた正式な法律文書であり、その内容には法的拘束力があります。一方、エンディングノートには法的効力が一切ありません。極端な例を言えば、エンディングノートに「財産は○○に全部譲る」と書いてあっても、それだけでは法律上その通りにはならないのです。
では、エンディングノートは無意味かというと、決してそうではありません。法的効力はなくても、本人の意思を知る大切な手がかりになりますし、遺言書には書けないことまで幅広く伝えられるメリットがあります。遺言書が主に財産の分配や相続に関する事項を法律上有効に定めるためのものなのに対し、エンディングノートは財産以外にも医療・介護の希望、葬儀の要望、心情的なメッセージなどあらゆることを書き残せる自由なノートです。ですから、遺言書の補完としてエンディングノートを活用すると良いでしょう。
もうひとつ重要な違いは、作成のハードルです。遺言書は自筆証書遺言なら決まった形式で全文を自書する必要があり、公正証書遺言なら公証役場で手続きを踏む必要があります。専門家に相談したり費用がかかったりと、どうしても構えてしまうものです。それに比べてエンディングノートは、紙とペンさえあれば今日からでも書き始められます。思いついたことを好きなように書ける気軽さがあるので、「まずはエンディングノートで希望を書き出し、その後必要に応じて遺言書に落とし込む」というステップでも良いでしょう。
まとめると、遺言書=法律に従って遺産相続を指定するための文書(法的効力あり)、エンディングノート=自由形式で思いや希望を伝えるノート(法的効力なし)という違いがあります。どちらか一方ではなく、状況に応じて両方を上手に活用することをおすすめします。
エンディングノートが実際に役立つ場面
エンディングノートは準備しておけば安心…とは言うものの、具体的にどんな場面でそれが活きてくるのでしょうか。考えられる活用シーンの一例を挙げてみます。
介護が必要になったとき
突然介護が必要になると、誰がどのように介護するか決めるのは家族にとって負担です。エンディングノートに「自宅で介護してほしい」「施設に入所する場合は○○ホーム希望」「できれば長男夫婦に中心になってほしい」といった希望を書いておけば、家族は方針を立てやすくなります。また認知症になった場合の財産管理や介護費用の手当についても事前に考えを書いておけば、周囲の混乱を減らせます。
入院や急病のとき
突然倒れて意識を失ってしまった場合、家族が医師から「延命措置をどうしますか?」などと尋ねられて慌てるケースがあります。エンディングノートに事前に終末期医療の希望(延命治療の可否や意思表示)を書いておけば、家族はその意思を尊重して医師と方針を決められます。また、持病やかかりつけ医、常用薬の情報がノートにまとまっていれば、救急搬送時にすぐ医療者へ引き継ぐことができます。入院の際に必要なものや連絡してほしい人のリストを残しておけば、家族がスムーズに対応できるでしょう。
相続手続きのとき
人が亡くなると、遺産相続の手続きを行わなければなりません。財産目録や通帳類がきちんと整理されていないと、相続人である家族は「どこに何の財産があるのか」探すところから始めなければならず、大変な労力と時間がかかります。エンディングノートで資産リストや保管場所が明確になっていれば、相続手続きを速やかに進めることができますし、相続人同士のトラブル防止にもつながります。遺言書がない場合でも、「生前に本人がこう望んでいた」という情報があるだけで、遺産分割の話し合いが円満にいくケースもあります。
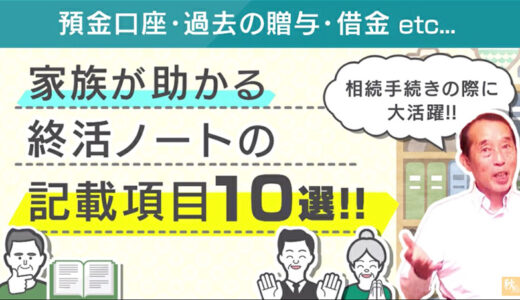 相続手続きの際に家族が助かるエンディングノートの記載項目10選! | 国税OB 税理士 秋山清成
相続手続きの際に家族が助かるエンディングノートの記載項目10選! | 国税OB 税理士 秋山清成
死後の手続きをするとき
ご逝去後、遺族は各種手続きを速やかに行う必要があります。役所への死亡届提出はもちろん、銀行口座の凍結解除、クレジットカードや携帯電話の解約、公共料金やサブスクリプションサービスの名義変更・停止、SNSやメールアカウントの整理など、細かな手続きが山ほどあります。エンディングノートにそうした「やるべき手続きリスト」や契約中のサービス一覧を書いておけば、家族は漏れなく対応できます。放置すると料金が引き落とされ続けたり、データが失われたりする恐れのあるものも多いので、事前に書き残しておく意義は大きいです。特にデジタル関係は見落とされがちなので、生前に自分で整理しておくと安心です。
このように、エンディングノートは介護・医療の現場から相続・事務手続きの場面まで幅広く役立ちます。実際の調査でも、75歳以上の高齢者のうちエンディングノートを「準備している人」はわずか23.3%ですが、その人たちがノートを書いた理由には「親の急病時に終活の有難みを実感した」「自分の死後に家族が困らないように」というものが上位に挙げられています。エンディングノートは万一のときに備える家族への思いやりであり、いざというとき本当に役に立つ「人生の備え」なのです。
葬儀の情報を事前に集めておく大切さ
エンディングノートの内容とも関わりますが、葬儀に関する情報を事前に集めておくこともとても大切です。葬儀は突然のことで家族が慌てがちな場面です。もし何の準備も情報もないと、悲しみの中で式場探しや費用の比較を急いで行わねばならず、精神的・経済的負担が大きくなります。逆に生前にある程度情報収集しておけば、「どの葬儀社に依頼するか」「どんな規模で行うか」の見当がつき、家族は安心して送り出しの儀式に臨めます。
事前の情報収集でできること: 葬儀社のパンフレットを取り寄せてプランや費用を把握しておく、希望する葬儀の形式(例えば家族葬や直葬など)がある場合は対応している業者を調べておく、葬儀費用の相場を知って貯蓄計画に反映させておく、などが可能です。最近ではインターネットで簡単に資料請求ができますので、気になる葬儀社があれば早めに資料を取り寄せて比較しておくと良いでしょう。
例えば、全国対応の葬儀サービス「小さなお葬式」では、無料で資料請求が可能です。事前にそうした資料を手元に揃えておけば、万が一の際にも慌てずに済みますし、生前に家族と葬儀について話し合うきっかけにもなります。「小さなお葬式」のように事前相談や資料請求をすると割引特典(5万円)が受けられるサービスもあります。経済面でも準備しておくメリットがあると言えるでしょう。
大切なのは、「知らないままより、知って備えておく方が安心」ということです。エンディングノートに葬儀の希望を書く際にも、具体的なイメージや費用感をつかんでおけば書きやすくなります。ぜひ前向きに情報収集を行い、ご自身とご家族の安心につなげてください。
まとめ
エンディングノートは決して「死の準備」だけを目的としたものではなく、これからの人生をより安心して、自分らしく生きるためのサポートツールです。高齢になってからでも遅くありません。思いやりと希望を込めた一冊を用意しておくことで、残りの人生を穏やかな気持ちで過ごせることでしょう。今日できる小さな一歩として、エンディングノートを書き始めてみませんか。ご自身と大切な家族のために、きっと役立つはずです。