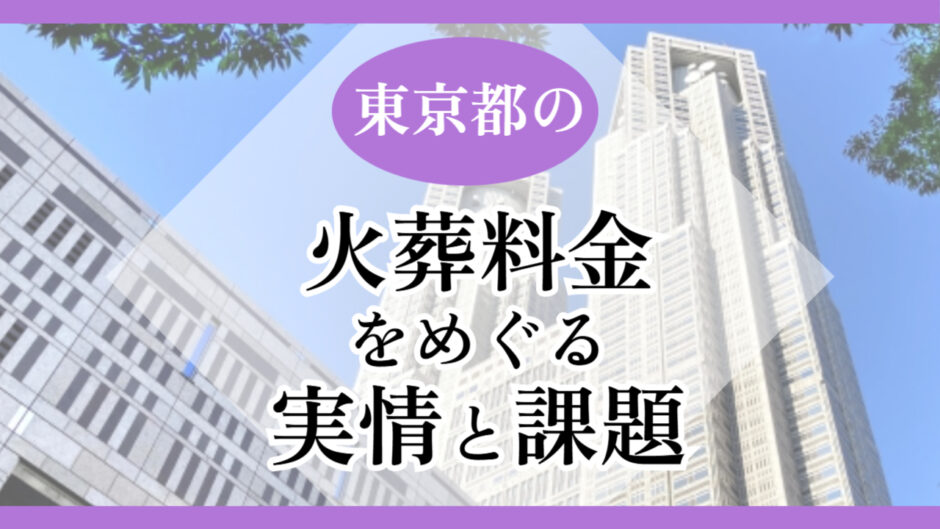東京都における火葬料金の高騰が深刻な問題となる中、2025年9月30日、東京都は23区内の火葬場について料金や運営実態を把握するための調査を開始する方針を明らかにしました。
23区内の火葬場は9か所と限られており、このうち公営施設は臨海斎場と瑞江葬儀所のわずか2か所です。
公営施設の料金は、臨海斎場が44,000円(組織区内住民)、瑞江葬儀所が59,600円(都民)となっています。一方、民営施設では約9万円が相場となっており、近隣の横浜市(市民12,000円)や川崎市(市民6,750円)と比較すると、その差は歴然としています。
この記事では、なぜ東京の火葬料金がここまで高くなっているのか、その背景にある制度的な課題について詳しく解説します。
目次
なぜ今、東京都は火葬場の実態調査に踏み切ったのか

2025年9月30日の発表で、東京都は23区内の火葬場における料金設定や運営状況について実態調査を行うことを表明しました。
23区内には9つの火葬場がありますが、公営は臨海斎場と瑞江葬儀所の2つだけという状況です。このため、多くの都民は民営施設を利用することになり、約9万円という高額な費用負担を強いられています。
隣接する横浜市や川崎市では、市民向けに1万円前後で火葬サービスが提供されていることを考えると、東京都民の負担の重さは明らかです。今回の調査は、こうした大きな格差がなぜ生じているのか、その原因を明らかにしようとする取り組みといえるでしょう。
調査の目的と期待される成果
東京都が今回の調査で明らかにしようとしているのは、次のような点です。
- 各火葬場の料金がいくらに設定されているか
- 料金がどのような基準で決められているか
- 実際の運営がどのように行われているか
公営施設が少なく民営が中心という現在の状況において、料金設定は適正なのか、行政による監督や支援は十分なのかといった点を、具体的なデータとして把握することが重要です。
実態が明確にならなければ、料金設定の妥当性を評価することも、混雑を解消するための対策を立てることもできません。
今回の調査は、火葬料金がどのように決まっているのかを明らかにし、必要であれば公営施設の拡充、利用者への補助制度の創設、新たな規制やルールの策定といった具体的な施策につなげるための第一歩となります。
火葬料金の格差が浮き彫りに
現在の東京都内では、火葬料金に著しい格差が存在しています。
- 公営
臨海斎場:44,000円(組合区内住民向け)
瑞江葬儀所:59,600円(都民向け) - 民営
約9万円が標準的な料金
これに対して近隣自治体の状況を見ると、横浜市では市民向けに12,000円、川崎市では市民向けに6,750円で火葬サービスが提供されています。
誰もが必ず利用することになる火葬というサービスにおいて、なぜこれほど大きな料金差が生じているのか。多くの都民が抱くこの疑問は、きわめて当然のものです。今回の調査は、この疑問に答えを出すための重要な取り組みとなるでしょう。
 自治体でこんなに違う! 公営斎場の火葬料金と式場利用料
自治体でこんなに違う! 公営斎場の火葬料金と式場利用料
なぜ「いま」調査が始まったのか
調査を始めた理由はいくつかあります。まず民営施設での段階的な値上げにより、相場がこの数年で9万円前後まで押し上げられたことがあります。次に、公営施設がわずか2施設しかないという供給面での制約が、利用者を民営施設に依存させやすい構造を作り出していることも大きな要因です。
加えて混雑により希望する日程での予約が取りにくくなっており、これが遺体の安置や搬送などの付帯費用や手間を増加させ、利用者の体感的な負担をさらに重いものにしています。
こうした状況に加え、近隣自治体の公営料金との分かりやすい格差も明確になってきました。これらの現実が積み重なった結果、都はまず実態を正確に把握する必要があると判断し、調査に乗り出したということです。
東京都の火葬・葬儀の実情

東京都で火葬料金が家計の負担となっている背景には、火葬場の数が少ないことと、その運営形態に偏りがあることが挙げられます。
23区内には火葬場が9か所しかありません。このうち公営施設は臨海斎場と瑞江葬儀所の2か所だけで、残りの7か所は民営施設です。そのため、多くの都民は民営施設を利用せざるを得ない状況となっています。
料金を比較すると、民営施設は約9万円、公営の臨海斎場は44,000円(組合区内住民)、瑞江葬儀所は59,600円(都民料金)となっています。さらに、近隣自治体の公営施設(横浜市12,000円、川崎市6,750円)と比べると、その差はより明確です。
料金の高さに加えて、予約が取りにくいという問題も、都民の負担を増やしています。
火葬施設の不足と混雑
東京都全体では26の火葬場が稼働していますが、23区内では9施設にとどまります。人口規模に対して火葬炉の数が少ないため、亡くなる方が多い時期や、希望が集中する時間帯には予約が埋まってしまい、数日から1週間待つこともあります。
待機期間が長くなると、ご遺体の安置や搬送にかかる費用も増えていきます。施設不足による混雑で、結果的に料金の高い民営施設を選ばざるを得ない状況が生まれています。
公営施設が少ない東京の特殊性
全国的に見ると、火葬場は自治体が運営することが一般的で、住民向けの料金は無料から2万円程度の地域がほとんどです。
しかし23区では公営施設が2か所しかないため、火葬料金は民営施設の運営コスト(設備の更新費用、燃料費、人件費、税金など)に大きく左右されます。公営施設の料金設定があっても、実際には約9万円の民営施設を利用する方が多いのが現状です。
また、民営施設の多くが同一グループによって運営されているため、公営施設が料金の基準として機能しにくくなっています。
葬儀の多様化と高額な火葬料金の矛盾
近年、直葬・一日葬・家族葬といった小規模な葬儀が増えています。しかし、どのような形式を選んでも必ず必要となる火葬の料金が高いままでは、葬儀全体の費用はそれほど下がりません。
直葬を選んでも火葬料金が重くのしかかり、一日葬や家族葬でも同じ問題に直面します。
葬儀の形式は多様化したものの、高額な火葬料金がネックとなって、実際には希望に沿った葬儀を行いにくいという矛盾が生じています。東京では、この問題が特に顕著に表れています。
 一日葬とは?一般葬・家族葬・直葬との違いから流れ・費用まで徹底解説
一日葬とは?一般葬・家族葬・直葬との違いから流れ・費用まで徹底解説
都民が感じる二重の負担
多くの都民が感じているのは、料金の高さと利便性の低さという二重の負担です。
東京都の火葬料金は民営約9万円、公営4~6万円台であり、近隣自治体の公営約1万円料金と比べると明確な差があることに加え、予約の取りにくさが追加の費用や手間を生み出しています。
高額な料金と不便な運用が重なることで、都民の納得感は得られにくくなっています。こうした状況の積み重ねが、東京都に対して火葬場の実態を改めて詳しく調査し、改善策を検討する必要性を示しています。
なぜ東京の火葬料金は高いのか

東京の火葬料金が高額になっている背景には、公営施設の不足という根本的な問題に加えて、大都市特有のコストや需要の集中が複雑に絡み合っています。
ここでは運営構造の問題をはじめ、価格決定のメカニズムや利用者が実際に感じる負担について、順を追って見ていきましょう。
公営施設が少なく民営に依存
本来、公営施設は低価格でサービスを提供し、市場全体の料金水準を抑える役割を果たします。しかし、公営施設が少ない地域では、民営事業者が自由に料金を設定できる余地が大きくなり、結果として料金は事業者の利益を確保できる水準まで上昇しやすくなります。
23区内の火葬場9施設のうち7施設が民営という現状では、民営施設は公営の低料金を意識することなく、独自に高い料金を設定できてしまいます。そのため、2020年代に入ってから段階的な値上げが続き、現在では民営施設の料金は約9万円が主流となりました。
一方、公営施設は臨海斎場が44,000円、瑞江葬儀所が59,600円と、民営との差は数万円規模に広がっています。公営施設の不足が民営への依存を生み、それが料金の上昇圧力となるという連鎖が、東京の火葬料金を構造的に押し上げているのです。
大都市特有のコストの高さ
東京のような大都市では、土地の取得や施設の建設費、維持管理費が地方より高額になります。さらに、排気ガスや騒音といった環境問題への対策も、より厳格な基準が求められます。
これらの費用は固定費や設備更新費として積み重なり、最終的には利用料金に反映されることになります。公営施設が多い地域では、こうしたコストを公費で吸収できますが、民営施設の割合が高い東京では、料金に直接転嫁されやすいのが実情です。
近隣の横浜市や川崎市の公営施設(約1万円)と23区の民営施設(約9万円)との大きな差は、単純な価格競争の問題ではありません。大都市のコスト構造と運営形態の違いが組み合わさった結果として理解する必要があります。
施設の老朽化と改修の遅れ

都市部での火葬場の建て替えや増設は、用地確保の困難さに加えて、周辺住民の理解を得るのにも長い時間を要します。そして施設の改修が遅れれば遅れるほど、改修費用は高額になっていきます。
最新の火葬炉の導入や環境基準への対応まで含めると、その費用は最終的に利用料金を押し上げる要因にもなります。新たな施設を建設して供給を増やそうとしても、環境基準のクリア・地域住民からの同意・資金調達といった課題が立ちはだかり、短期間での解決は困難です。
結果として改修費用が料金に上乗せされ、供給不足も解消されないという二重の問題が生じています。
需要集中で混雑が慢性化
人口が集中し、死亡件数も多い東京では、火葬炉の数が需要に追いつかなければ、混雑は避けられません。この混雑は単なる「順番待ち」という時間的なコストだけでなく、ご遺体の安置や搬送といった追加費用の発生にもつながります。
需要が集中し、待機時間が発生し、それが付帯費用の増加を招くという流れで、利用者の実質的な負担は増大していきます。料金の高さと利用の不便さが相互に影響し合い、「高いうえに不便」という印象が定着してしまいます。
この状況を改善するには、供給を増やすか、公営施設による価格の下支え機能を強化するか、いずれかの構造的な対策が必要です。しかし、どちらの方法を選ぶにしても、現在の構造に手を加えない限り、料金の高止まりは続くと考えられます。
東京都の火葬料金に見える問題点

東京の火葬料金は、公営施設が少ないという構造的な問題に、大都市ならではの高コストと需要の集中が重なることで高止まりしています。その結果、経済状況に関わらず誰もが必要とする火葬において大きな地域格差が生まれ、希望する葬儀の形を選ぶ自由さえ制限される事態となっています。
東京都の調査は、この悪循環をどこで断ち切り、改善への道筋をつけるかを考える重要な第一歩となるでしょう。
地域間で広がる不公平
火葬料金の高さは、都民の家計に重い負担となっています。全国の多くの自治体では公営施設の住民料金が1万円前後であるのに対し、23区で利用される民営施設は約9万円が相場となっています。
同じ火葬というサービスで、これほどまでに料金差があることは、明らかな地域間格差といえるでしょう。さらに予約が取りにくい状況が続くことで、ご遺体の安置や搬送といった追加費用も発生し、実質的な負担はより大きくなっています。
すべての人に平等であるべき火葬サービスの公平性をどう確保するか。これは、もはや先送りできない重要な行政課題となっています。
高額料金が葬儀の選択肢を狭める
近年、直葬・一日葬・家族葬といったシンプルな葬儀形式が広まってきました。しかし、どの形式を選んでも必須となる火葬の料金が高いままでは、葬儀全体の費用はそれほど下がりません。
葬儀を簡素にしても、高額な火葬料金がネックとなって、費用削減の効果を打ち消してしまいます。その結果、経済的な理由から、本来望んでいた葬儀の形を諦めざるを得ないという矛盾が生じています。
葬儀の形が多様化すればするほど、火葬料金の高さという問題がより鮮明に浮かび上がってきます。
 「小さなお葬式」の火葬式プランとは?|費用・流れと「よりそうお葬式」との違い
「小さなお葬式」の火葬式プランとは?|費用・流れと「よりそうお葬式」との違い
火葬場はインフラとしてどうあるべきか
水道やごみ処理と同様に、火葬は市民生活に欠かせない基本的なインフラです。しかし23区では公営施設が少ないため、料金は民間市場の論理に左右されやすくなっています。
ここで問われているのは、火葬サービスの費用を誰が・どこまで・どのような方法で負担すべきかという制度設計の問題です。公営施設を増やして料金の基準となる役割を強化するのか、民営施設に対して料金設定の透明性や上限の目安を求めるのか、あるいは両方の対策を組み合わせるのか。
火葬場の公共インフラとしての位置づけを、改めて見直す時期に来ています。
火葬料金問題の解決に向けた第一歩となるか

東京都の火葬場実態調査は、長年見過ごされてきた問題に光を当てる重要な一歩となりました。23区内で公営施設がわずか2か所という現状が、約9万円という高額な火葬料金の背景にあることが明らかになってきています。
火葬は誰もが必ず利用する、生活に欠かせないサービスです。それにもかかわらず、近隣の横浜市や川崎市との料金差が7~8万円にも達する現状は、多くの都民にとって納得しがたいものでしょう。さらに、予約の取りにくさによる待機期間の長期化は、精神的な負担に加えて経済的な負担も増大させています。
葬儀の形が多様化する中で、火葬料金の高さが「最後の壁」となって、希望する弔い方を選べないという矛盾も生まれています。簡素な葬儀を選んでも、火葬料金だけは削減できないという現実は、真の選択の自由を奪っているといえるかもしれません。
今回の調査をきっかけに、火葬場が持つ公共インフラとしての性格を改めて認識し、料金の透明性確保や供給体制の改善など、様々な角度からの検討が期待されます。
すべての都民が経済状況に左右されず、尊厳ある最期を迎えられる環境づくり。それこそが、この問題の本質的な解決につながるのではないでしょうか。