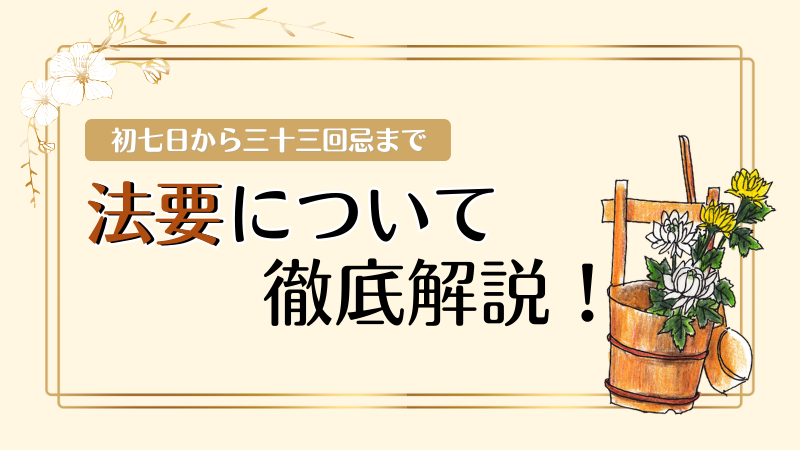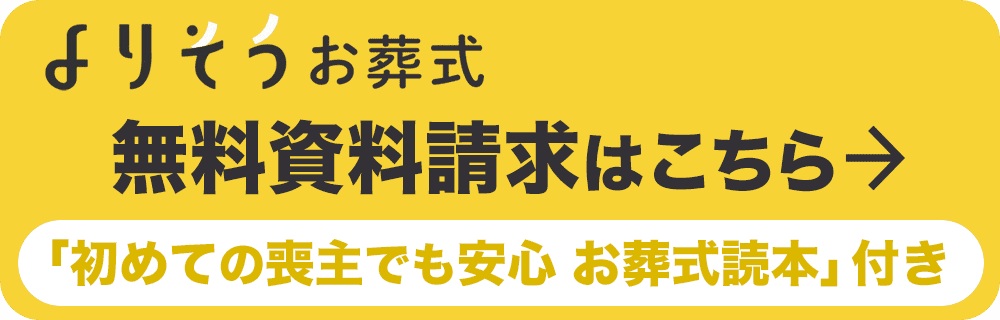近年は法要を簡素化する家庭も増えていますが、葬儀で大切な人を見送ったあとも、初七日・四十九日・一周忌・三回忌など、節目ごとに法要は続きます。
本記事では、初めて遺族となる方に向けて、これら年忌法要の種類と意味を分かりやすく紹介します。宗派ごとの違いや準備・マナーも解説し、先祖供養を正しく理解しながら故人を偲ぶための情報をお届けします。
目次
葬儀後の法要とは ― 忌日法要

葬儀を終えたばかりの遺族が次に向き合うのが、故人をしのぶ「法要」です。法要には日数ごとに営む忌日(きにち)法要と年ごとに営む年忌法要があります。
本章では忌日法要に焦点を当て、その意味や流れ・準備のポイントを解説します。
忌日法要とは
忌日法要は、故人の亡くなった日から七日ごとに行う供養です。仏教では人は亡くなってから七日ごとに冥府で審判を受け、七七日(なななのか)=四十九日で来世が定まると説かれます。
遺族は読経と焼香を通じて故人の成仏を願います。最初の節目が初七日(しょなのか)で、命日を1日目として数え7日目に営まれます。最近は葬儀当日に繰り上げて済ませる「繰り上げ初七日」が一般的になりつつあります。
主な忌日法要の呼称
ここでは、主な忌日法要の呼称を一覧でまとめてご紹介します。
| 呼称 | 読み方 | 日数 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 初七日 | しょなのか | 7日目 | 三途の川で最初の審判。繰り上げ初七日が増加。 |
| 二七日 | にしちにち/ふたなのか | 14日目 | 2回目の七日目。遺族で小規模に読経。 |
| 三七日 | さんしちにち/みなのか | 21日目 | 同上 |
| 四七日 | よなのか | 28日目 | — |
| 五七日 | ごしちにち | 35日目 | 三十五日法要。地域によってはここで忌明け。 |
| 六七日 | ろくしちにち | 42日目 | — |
| 七七日(四十九日) | しちしちにち | 49日目 | 忌明け法要。納骨・本位牌開眼を行うのが一般的。 |
四十九日(忌明け法要)の意義
仏教では、人は亡くなると七日ごとに冥府で審判を受け、七七日(49日目)で来世が決まるとされます。遺族が読経と回向を重ねることで、故人の成仏とよりよい来世を願う──これが忌日法要の本質的な考え方です。四十九日で「忌明け」となり、喪服や香典辞退などの制限が解かれ、年忌法要へと移行します。
ただし、忌明けの時期や供養方法には地域や宗派で違いがあります。たとえば「三月越え」を避ける地域では、五七日(35日目)で忌明けを行うことが一般的です。また、浄土真宗本願寺派の一部でも三十五日を区切りとする場合があります。法要時に立てる塔婆も宗派で異なり、曹洞宗や真言宗では立てるのが通例ですが、浄土真宗では教義により塔婆供養を行いません。
同じ宗派でも寺院ごとに解釈が異なることがあるため、準備を進める際は菩提寺に確認し、地域の慣習に沿って進めることが大切です。
忌日法要の準備のポイント
四十九日までの準備を進めるなかで、「誰を招くか」「いつ案内状を出すか」「お布施や引き出物はいくらが目安か」などの判断に迷う遺族は少なくありません。
ここでは、初七日から四十九日までに必要な準備と相場費用をまとめました。地域や寺院の慣習によって幅はありますが、次のポイントを押さえておくと計画が立てやすくなります。
-
参加者の確認
初七日と四十九日は親族以外の友人・知人も招くことが多いが、二七日~六七日は近親者のみで簡素に行うのが一般的。 -
案内状の送付
四十九日は往復はがきを用いて案内状を送付。1か月前には発送し、法要の1~2週間前には出欠確認ができるようにする。 -
お布施相場の確認
初七日・四十九日は3万~5万円前後、二七日以降は1万~3万円前後が目安。 -
引き出物の手配
日持ちするお茶・菓子類が無難。会食を省略する場合はやや高めの品に。
忌日法要は、亡くなった直後から四十九日までの約1か月半、遺族が故人と向き合い続ける大切な時間です。形式ばかりにとらわれず、七日ごとに静かに手を合わせ、思い出を語り合うことで心の整理も進みます。
主要な年忌法要

初七日・四十九日の忌日法要を終えると、一周忌、三回忌、七回忌…と年忌法要が続きます。ここでは、それぞれの法要が迎える時期(没後〇年目)と、その法要に込められた意味、現代における位置づけを解説します。
遺族として準備すべきことや宗派による違いについても触れていきますので、各年忌法要への理解を深めましょう。
一周忌(満1年目) – 喪明けと故人を偲ぶ大切な節目
一周忌は、故人が亡くなってから丸1年後の命日に営む最初の年忌法要です。四十九日から約10か月が経過し、遺族の生活も徐々に日常を取り戻す頃にあたります。
多くの家庭では一周忌までを喪中と位置づけ、この法要をもって喪明けとする場合が一般的です。天台宗などでは「百か日を経て一周忌を迎えると喪が明ける」とされています。一周忌法要は、遺族にとって大きな節目であり、親族や故人と親しかった友人知人を招いて営まれることが多く、会場は菩提寺・自宅・本堂などさまざまです。
僧侶による読経・焼香の後に会食を設けるのが通例で、故人を偲ぶひとときとなります。地域によっては、喪明けの時期を四十九日とする場合もあります。
なお、近年はお寺との付き合いが薄く、僧侶への依頼に悩む方も少なくありません。その場合はよりそうお坊さん便のような全国対応の僧侶手配サービスを利用すると、準備の負担が軽減されます。
三回忌(満2年目) – 節目の法要と現在の傾向
三回忌は、故人が亡くなってから2年目の祥月命日に営む年忌法要です。仏教では三と七のつく年が供養の節目とされており、三回忌は一周忌に続く大切な法要です。参列者は故人と縁の深い親族・知人が中心となり、比較的規模のある形で行われることが多く、服装も一周忌と同様に喪服が基本とされます。
現代では三回忌を区切りとし、それ以降の年忌法要は省略する家庭も増えています。背景には核家族化や遠方在住の親族の増加など、集まりにくい社会状況があります。
一方で、信仰心の厚い家庭では五十回忌や百回忌まで行うこともあり、どの法要まで営むかは家の方針や菩提寺の考え方によって異なります。
七回忌・十三回忌以降 – ご先祖の仲間入りと弔い上げ
七回忌は故人没後6年目、十三回忌は12年目の命日に営まれる年忌法要で、仏教では「七」のつく年を節目とし重視されてきました。
特に十三回忌は一回忌から数えて13回目にあたり、かつては親族が多く集う大切な法要とされていましたが、近年は核家族化や高齢化などを背景に、七回忌以降は省略したり、近しい親族のみで営む家庭も増えています。
そして一連の年忌法要の締めくくりにあたるのが「弔い上げ」で、仏教では三十三回忌(没後32年目)をもって故人が完全に成仏し、先祖として迎えられると考えられています。これは、30年以上経つと故人を直接知る人が少なくなり、世代交代の節目でもあることから区切りとされているためです。実際、多くの永代供養墓では三十三回忌をもって合祀へ切り替える例が多く見られます。
ただし、宗派によって考え方は異なり、日蓮宗では弔い上げという区切りは設けず、子孫が続く限り供養を行うとされ、浄土真宗では故人はすぐ浄土へ往生するという考え方から、法要はあくまで遺族が故人を偲ぶ場とされます。
法要の継続や終え方は家庭や地域、宗派の教えによって異なるため、住職や親族と相談の上、無理のない形で計画することが大切です。
*年忌法要の年数と名称まとめ
-
一周忌 – 没後満1年目(喪明けの法要)
-
三回忌 – 没後満2年目(最初の節目となる年忌法要)
-
七回忌 – 没後満6年目
-
十三回忌 – 没後満12年目
-
十七回忌 – 没後満16年目
-
二十三回忌 – 没後満22年目
-
二十七回忌 – 没後満26年目
-
三十三回忌 – 没後満32年目(弔い上げとするのが一般的)
-
五十回忌 – 没後満49年目(宗派や篤信の家ではここを弔い上げとする場合も)
-
百回忌 – 没後満99年目(まれに行われる大法要)
なお、上記の年忌以外にも百箇日(ひゃっかにち)法要や、新盆(初盆)と呼ばれる初めてのお盆の供養など、故人を偲ぶ行事があります。
百箇日は「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれ、遺族が悲しみを卒業する日と位置づけられることがあります。新盆(初盆)は忌明け後に初めて迎えるお盆で、特に丁重に故人の霊を迎える行事です。
地域によっては白提灯を飾って新盆供養を行う習慣もあります。これらも年忌法要とあわせて覚えておくとよいでしょう。
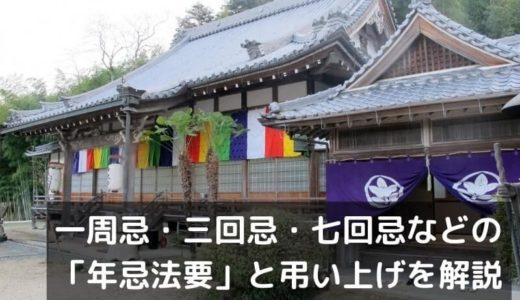 一周忌・三回忌・七回忌…年忌法要と弔い上げをわかりやすく解説
一周忌・三回忌・七回忌…年忌法要と弔い上げをわかりやすく解説
年忌法要の準備とマナー

年忌法要を滞りなく営むためには、事前の準備や当日のマナーにも気を配る必要があります。ここでは、法要の日程調整や僧侶への依頼、会場や会食の手配、親族への案内状送付、当日の服装や引き出物の準備など遺族が押さえておきたい基本的な流れとマナーを解説します。
初めて法事を主催する方でも安心して臨めるよう、公的な手続きや寺院との打ち合わせポイントも確認しておきましょう。
法要日程の決定と菩提寺への依頼
年忌法要の日程は命日当日が望ましいですが、平日で都合が悪い場合は命日前の直近の土日祝日に行うのが一般的です。まずは菩提寺に連絡し、希望の日時で僧侶に読経をお願いできるか相談しましょう。
お寺の法要スケジュールは春秋の彼岸やお盆、年末年始など混み合う時期もありますので、少なくとも2か月前には問い合わせるのがおすすめです。
日程が決まったら、寺院で法要を行う場合は本堂の予約は不要ですが、もしお墓の前や自宅、または貸し会場で行う場合はその手配も行います。会食を設けるなら、近隣の料亭や仕出しの手配もこの時点で検討しておきましょう。
なお、お寺以外の場所で法要を営む場合、菩提寺が遠方だと僧侶にお車代(交通費)を多めに包む必要が出ますので、可能なら寺院近くの会場を手配すると負担が軽減できます。
案内状の送付と招待客の範囲
法要の日程と場所が決まったら、参列してほしい方々に案内状を送りましょう。一般的には1か月前までに発送し、返信期限は法要の1~2週間前くらいに設定します。案内状には往復はがきを使用し、仏事用の切手を貼るのがマナーです。
文面には日時・会場・故人名・法要の種類、会食の有無や服装について明記し、返信用はがきには出欠と人数記入欄を設けて準備に役立てます。参列者が少人数だったり、郵送を省略したい場合は電話やメールでの連絡でも構いません。
誰を招待するかは法要の規模や種類によって異なります。初七日や四十九日、一周忌などでは親族に加え、故人と親しかった友人知人にも広く案内することが多い一方で、三回忌以降は家族や近親者だけで執り行う傾向が一般的です。
遠方の親戚には一周忌まで声をかけ、それ以降は近場の親族のみとするなど、各家庭の事情に応じて無理のない範囲で調整するとよいでしょう。
引き出物やお布施の準備
出欠の返事が揃い始めたら、参列者への返礼品を用意します。法要に来ていただいたお礼として渡す品物で、一般的にはお茶や海苔、お菓子など日持ちする消えものに、のし紙を掛けて用意します。法要当日に持参してもらうか、事前に配送しておく方法もありますが、なるべく法要前日までに届くよう手配しておくと安心です。
品物の金額は会食を行う場合と行わない場合で異なりますが、一人あたり3千~5千円程度が目安とされます。また、遠方からの参列者には別途お車代を包むことも検討しましょう。
お布施については、一般的な目安があります。例えば一周忌法要のお布施相場は3万~5万円程度、それ以降の法要は1万~3万円程度とも言われます。
お布施は黒白の水引が印刷された奉書封筒に包み、表書きは「御布施」、下に施主の姓名を記します。お寺への挨拶時に本堂の折敷などにのせてお渡ししましょう。また、僧侶に遠方から来てもらう場合のお車代や、会食を辞退された際のお礼として御膳料を包むこともあります。
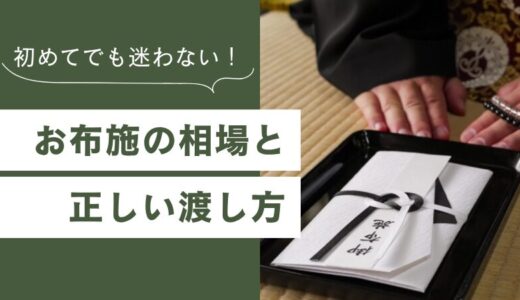 初めてでも迷わない!お布施の相場と正しい渡し方
初めてでも迷わない!お布施の相場と正しい渡し方
当日の服装とマナー
法要当日の服装は、基本的に喪服が無難とされています。初七日から一周忌までは遺族・参列者ともに正式な喪服を着用するのが一般的ですが、三回忌以降は略式の喪服(平服)でもよいとされる場面が増えています。
ただし平服といってもカジュアルすぎる服装はマナー違反となるため注意が必要です。男性はダークスーツに黒ネクタイ、女性は黒や紺、グレーなど落ち着いた色合いのスーツやワンピースを選びましょう。小物も黒で統一し、華美なアクセサリーは避けます。子どもも制服や地味な色の服装を選ぶのが望ましく、季節に応じた服装でも派手な柄は控えます。
当日は施主が開始30分前には会場入りし、僧侶や親族を迎えるのがマナーです。焼香の順番や進行を確認し、参列者にも丁寧に伝えましょう。会食がある場合は開宴の挨拶を、ない場合も一人ひとりに感謝の気持ちを伝え、心のこもった対応を心がけることが大切です。「本日は故〇〇の〇回忌にお集まりいただきありがとうございます」と感謝を述べ、故人の思い出に触れる一言を添えるとよいでしょう。
宗派や地域による違い

年忌法要の基本的な流れは仏教全般で共通していますが、宗派や地域によって細かな違いがあります。弔い上げとする回忌のタイミングや、年忌法要自体の意味づけなど、宗派ごとの考え方を押さえておくと、より深い理解につながります。
この章では代表的な仏教宗派における年忌法要の特徴や、神道・キリスト教の場合の追悼行事についても簡単に触れます。
宗派ごとの弔い上げの違い
仏教の主要宗派では、年忌法要を営む回数や弔い上げの考え方に若干の違いがあります。以下、いくつかの宗派の特徴を紹介します。
-
浄土真宗
一周忌から三十三回忌まで行い、三十三回忌で弔い上げとします。
浄土真宗では、年忌法要は故人の冥福を祈るというより「遺族が故人を偲ぶ場」と位置づけられます。故人はすでに阿弥陀如来の救いにより極楽往生しているとの教えに基づくためで、追善供養そのものを目的とはしない点が特徴です。 -
真言宗
年忌法要は十七回忌まで行い、その後は二十三回忌と二十七回忌を省略して二十五回忌を営むのが一般的です。
弔い上げは三十三回忌としますが、その後も五十回忌・百回忌・百五十回忌…と長期間にわたり法要を行うことも特徴です。 -
曹洞宗
基本的に十七回忌まで行い、その後は二十三回忌・二十七回忌を行うか、あるいは二十五回忌としてまとめて行います。弔い上げは多くの地域で三十三回忌ですが、寺院によっては五十回忌まで勧めることもあります。 -
臨済宗
十七回忌まで行った後は、地域により二十三回忌を行う所と二十五回忌を行う所に分かれます。いずれにせよ三十三回忌をもって弔い上げとし、それ以降は行わないことが多いようです。 -
天台宗
十七回忌まで行い、二十三回忌・二十七回忌は省略して二十五回忌を営むことが多いです。弔い上げは三十三回忌です。なお、天台宗では納骨を終えて忌明け、その後百箇日を経て一周忌で喪明けとする習慣があります。 -
日蓮宗
他宗派と異なり、決まった弔い上げの考え方がありません。三十三回忌以降も法要は続けられ、法要を執り行う子孫が亡くなった時点で事実上の弔い上げになる、という考え方をします。つまり故人の供養を絶やさないことを重んじる宗派と言えます。
現在では各家庭の事情を優先して年忌法要の回数を決める傾向があります。菩提寺がある場合は宗派の習わしも踏まえつつ、住職と相談して柔軟に決めるとよいでしょう。
神道・キリスト教の場合
神道・キリスト教では、年忌法要にあたる追悼行事にどのようなものがあるか紹介します。
-
神道
法要にあたる行事は霊祭(れいさい)と呼ばれます。亡くなってから数えて50日目に五十日祭、100日目に百日祭を行い、その後は一年祭、三年祭、五年祭、十年祭、二十年祭…と続きます。多くは三十年祭をもって弔い上げとします。 -
キリスト教
仏教のような年忌供養の概念はありませんが、日本では一種の風習として命日に近い時期に記念集会や追悼ミサが行われることがあります。一般的には亡くなってから1年以内に一度追悼の礼拝を行い、その後毎年行う習慣はありません。故人は亡くなると神のもとへ召されるという教えから、仏教式の「弔い上げ」も本来ありません。
自分の家がどの宗教・宗派かを改めて確認し、それに沿った形で供養を続けることが大切です。分からない点は菩提寺や詳しい親族に尋ねながら、無理のない範囲で年忌法要を勤めていきましょう。
まとめ

葬儀後に続く年忌法要は、故人の冥福を祈りつつ遺族の心の整理をつけていく大切な伝統行事です。一周忌・三回忌など主要な法要にはそれぞれ意味があり、仏教の教えに基づく節目として位置づけられています。
現代では家族形態の変化により法要の簡略化もみられますが、故人との絆を再確認し感謝と思い出を共有する機会として法要を営む意義は色褪せません。年忌法要の種類やスケジュール、準備の仕方やマナーを理解し、無理のない形でご供養を続けていきましょう。
わからないことは遠慮なく菩提寺や専門の窓口に相談し、先祖供養の習わしを大切にしながら故人を偲ぶ時間を重ねていただければ幸いです。