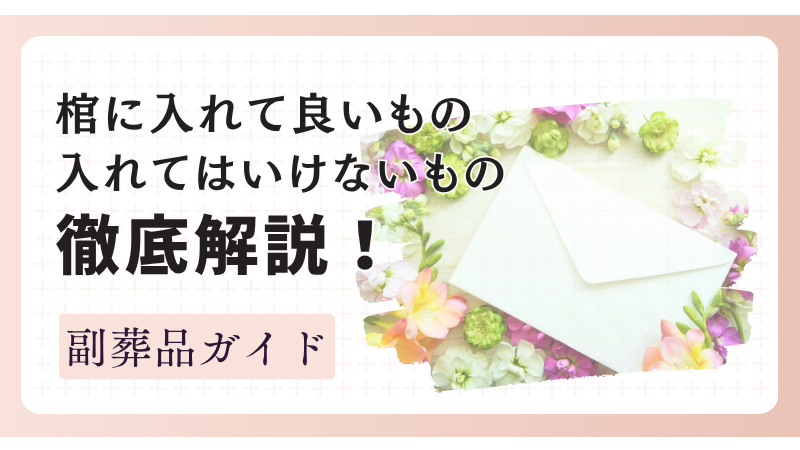愛する人の葬儀を考えるとき、故人との思い出の品を棺に納めて一緒に送ってあげたいと願う方は多いでしょう。副葬品として棺に入れられるものには、火葬の安全性や各自治体のルールによって入れて良いものと入れてはいけないものがあります。
本記事では、副葬品の意味や代表的な例、そして棺に入れてはいけない物の具体例を解説します。
地域や宗教による違いや注意点にも触れるので、安全かつ心温まる最後のお見送りの手助けになれば幸いです。棺に副葬品を納める際のマナーや法律も存在するため、正しい知識を持って大切な人を送り出しましょう。
副葬品の意味と役割

副葬品は古代より死者と共に埋葬する品として存在してきました。それらはかつて故人があの世で使う道具や供となる人形など、来世への備えとして意味を持っていました。
現代では副葬品は故人への弔いの気持ちや思い出を形にするものとなり、生前愛用した品々や家族からの手紙などが選ばれることが一般的です。まずは、副葬品に込められた意味とその役割について見ていきましょう。
副葬品とは
副葬品とは、故人と共に棺に納められ火葬される品物全般を指します。故人が生前大切にしていた愛用品や、家族との思い出の品、宗教的な道具など様々ですが、いずれも遺族の「感謝」や「祈り」といった気持ちを形にしたものです。
単なる物品以上に大切な意味を持つため、何を納めるかは慎重に考えたいところです。
古くから伝わる副葬品の風習
副葬品の風習は世界各地で見られ、日本でも古代から続いてきました。たとえば古墳時代には、衣服や武具は故人が来世で使用するため、人物・馬をかたどった土製品は従者や乗り物の代わりとして、副葬品に加えられていた記録があります。
実際、埴輪など多くの副葬品が一緒に出土する古墳も存在します。それだけ死後の世界へ持たせる品には重要な意味が込められていたのです。
現代における副葬品の役割
時代とともに副葬品の役割は変化し、現代では故人への弔いと想いを象徴する品が中心になりました。思い出の写真や手紙、愛用品の一部などを棺に納めることで、遺族は故人への想いを託し、心の区切りとすることができます。
副葬品を選ぶ過程そのものが、故人との思い出を振り返り送り出す準備にもなるでしょう。副葬品は形見として残す方法もありますが、火葬で一緒に送り出すことで故人と遺族双方の心の慰めになる点も現代の副葬品の大きな役割です。
副葬品の持つ意味
副葬品は単なる副次的な品ではなく、故人への最後の贈り物として深い意味を持ちます。古来より来世への備えとして様々な品が添えられてきましたが、現代では「ありがとう」「さようなら」の想いを込めた品を納めることで、心温まる見送りを実現しています。
まずはこうした副葬品の意味を理解し、故人に相応しい品を選ぶことが大切です。
棺に入れて良い副葬品と選び方

火葬では燃えやすく安全なものであれば副葬品として棺に納めることができます。ここでは、棺に入れて良いとされる代表的な副葬品を紹介します。
故人が愛用していた物や趣味にまつわる品、遺族からの手紙や写真など、心を込めて選びたいものです。品物を選ぶ際には素材や大きさにも注意し、火葬場のルールに従った上で故人らしさを表現できるものを選びましょう。
思い出を伝える手紙・写真
手紙や写真は定番の副葬品です。遺族が書いた手紙や故人が大切にしていた手紙を棺に納めることで、感謝や愛情の気持ちを直接伝えることができます。
また、故人と一緒に写った写真も思い出を共有する品としてよく選ばれます。ただし、生存している人が写っている写真を棺に入れることは避けるのがマナーです。
生者の写真を一緒に燃やすのは「共に彼岸へ旅立つ」といった俗説から縁起が悪いとされるためで、写真を選ぶ際には故人のみ、もしくはペットなど故人以外が写っていないものを選ぶと良いでしょう。
故人の趣味・愛用の品
故人の趣味や嗜好にまつわる品も、副葬品として人気があります。読書好きだった方にはお気に入りの文庫本や日記帳、音楽が好きだった方には楽譜や歌詞ノートなど、故人が生前愛したものを一緒に入れることでその人らしさを偲ぶことができます。
ポイントは、できるだけ紙や布など燃えやすい素材のものを選ぶことです。たとえばCDやレコードなどはそのままでは燃えないので棺に入れられませんが、CDのジャケットや紙製の歌詞カードだけを副葬品とすることはできます。
同様に、プラスチック製の模型や金属製のアクセサリーは避け、代わりに木製のものや布製のもので代替できないか工夫すると良いでしょう。
革製のミサンガなど、アクセサリー類は燃える素材であれば小さなものは一緒に収められるケースもあります。故人愛用の品を選ぶ際は素材に注意しつつ、「これがあの人らしい」という品を選びましょう。
自然素材の衣類や布製品
故人が愛用していた衣類や身の回りの布製品も、副葬品に適したものが多いです。例えば、お気に入りだった洋服や帽子、ハンカチなどは綿・絹・麻といった自然素材であれば問題なく火葬できます。
化学繊維ではなく天然素材の服を選ぶことで、燃え残りや有害物質の発生を防げます。また、故人が長年身につけていた布製の品(愛用のストールや布製の財布など)は、その人を象徴する副葬品になります。
特にお子様の場合、お気に入りのぬいぐるみを入れてあげたいという声も多いです。ぬいぐるみに関しては小さな布製のものであれば燃やせるため問題なく副葬品にできます。
ただし大きすぎるものや難燃性の素材を含むものは避け、心配な場合は事前に葬儀社へ相談すると安心です。布製品はいずれも清潔な状態で棺に納め、故人と過ごした時間の記憶を一緒に送り出しましょう。
数珠・お守りなど

故人が信仰を持っていた場合、宗教的な副葬品を棺に納めることもあります。仏式の葬儀で故人の手に持たせる数珠はそのまま火葬することが多く、数珠自体は木玉や糸でできていれば問題なく燃えるため副葬品にできます。なお、プラスチック製や金属製の数珠は入れることができません。
また、生前お守りを肌身離さず持っていた方なら、そのお守りを一緒に入れてあげるのも良いでしょう。紙製の経文や小型の聖書なども燃える素材であれば副葬品として納められます。
キリスト教の場合、ロザリオや小さな木製の十字架を入れることもあります。ただし硬貨・紙幣などの現金、メダイなどの貴金属製の宗教アイテムは棺に入れられません。
そのため、仏教の六文銭の風習などでは、紙に印刷された六文銭や木製の模型貨幣を使うのが一般的です。宗教的な品を入れる際も、素材と火葬場の規定を確認してからにしましょう。
故人の好きな食べ物・飲み物・花
副葬品として食べ物や飲み物を少量入れることもあります。故人が生前好んで食べていたお菓子や果物を一口大に切ったものなどは、燃えやすく問題ありません。
例えば甘党の故人には好きだったチョコレートやキャンディを数個、副葬品として入れることができます。ただし、スイカやメロンなど水分の多い果物を丸ごと入れるのは避けましょう。
大きな果物は火葬中に破裂する恐れがあるため、どうしても入れたい場合は皮を剥いて小さく切った状態で添えます。また、お酒やジュースなどの飲み物も故人が好きだったものを副葬品にできますが、瓶や缶の容器は燃えないためNGです。
紙パック入りの飲料や、中身を紙製の容器に移し替えたものを用意して棺に入れるようにしましょう。日本酒が好きだった方には紙製の小瓶に移し替えたり、故人愛用のお猪口に少量注いで一緒に入れてあげることもできます。
さらに、お花も忘れてはならない副葬品です。葬儀の最後には参列者が棺に花を入れる「棺花」の儀式がありますが、特に故人が生前好きだった花や季節の花を遺族の手で数輪入れてあげると良いでしょう。
花は香りも良く棺を華やかに彩り、故人への想いを込めるのにふさわしい副葬品です。これら食べ物・飲み物・花はどれも燃えやすいものを少量というのがポイントです。入れ過ぎは遺骨を覆う灰が増えてしまう原因にもなるため注意しましょう。
安心して入れられる副葬品を選ぶ
棺に入れられる副葬品は、基本的に火葬して問題のない素材でできた品物です。手紙や写真、布製の衣類・ぬいぐるみ、生花や少量の食べ物など、故人との絆を象徴しつつ安全に燃やせるものを選ぶと良いでしょう。
副葬品を選ぶ際は「故人が喜ぶか」「火葬場の規定に反しないか」を基準に、必要最小限の品に厳選することが大切です。また、地域や火葬場ごとの細かなルールがある場合もあるため、不安な点は事前に葬儀社や火葬場に確認しながら進めれば安心です。
たとえば「小さなお葬式」では、必要な準備や火葬場のルールに詳しいスタッフが丁寧に対応してくれるため、副葬品選びでも適切なアドバイスを受けられます。


棺に入れてはいけない副葬品とその理由

どんなに大切な品でも、火葬の過程で棺に納めることが禁止されている物があります。ここでは、棺に入れられない主な副葬品とその理由を説明します。
自治体や火葬場によって細部は異なるものの、燃えないものや危険物、燃えても遺骨に影響を与えるものなどは全国的に棺への納棺が禁止されています。
具体的にどのようなものが該当するのか、カテゴリごとに見ていきましょう。
金属・ガラス・陶器類:燃えずに残る
金属製やガラス製の品物、陶器類などの不燃物は棺に入れてはいけません。たとえば指輪・ネックレスなどの貴金属類、腕時計、眼鏡のフレームや入れ歯、ガラスの置物などが該当します。
これらは高温でも燃えずに溶け残ったり破片が遺骨に付着したりする恐れがあります。実際、火葬後の遺骨に溶けた金属やガラス片が付くと骨壺に収める際に支障が出ますし、場合によっては遺骨を傷つけてしまいかねません。
また、火葬炉の中で金属が高温で溶解・膨張して炉を傷めるリスクも指摘されています。陶器や磁器といった焼き物も燃えずに残るため、副葬品にはできません。同様に、硬貨などの貨幣類も金属ですので燃え残ってしまいます。
金属製品やガラス製品は故人の遺品として形見に分けたり、写真に撮って納めたり別の形で供養するようにしましょう。
プラスチック・革・ゴム製品:有毒ガスや遺骨の損傷の原因
プラスチック製品やビニール・ゴムなどの合成素材でできた物も棺に入れられません。これらは燃やすと有毒なガスや黒煙が発生し、火葬炉内の環境を悪化させます。
特に塩化ビニールやウレタン素材が燃焼するとダイオキシン類の有害物質が発生するため、環境面・作業者の安全面から厳禁です。また、プラスチックやゴム類は不完全燃焼を起こしやすく、煤(すす)や溶けた残留物が遺骨に付着して汚してしまうこともあります。
具体的には、ビニール製のバッグや合成皮革の靴、ゴム製の人形やおもちゃ、プラスチック製のフィギュアなどが該当します。これらは副葬品として入れたいと希望されることもありますが、火葬場では受け入れてもらえないので注意しましょう。
ポリエステルやナイロンなどの化学繊維の衣類も燃える際に有害ガスが出たり溶けて塊になり遺骨に付くためNGです。遺骨の変色や損傷につながる恐れがあるものは、故人のためにも避けるのが賢明です。
スプレー缶・ライター・電池類:爆発の恐れ

火葬中に爆発・破裂する危険のあるものも厳禁です。代表的なのが高圧ガスを含むスプレー缶やオイルライター、そして電池類です。
これらが棺の中に入ったまま火葬炉の高温にさらされると、内部のガスや液体が膨張し爆発を起こす可能性があります。実際に、過去には遺族が気づかず棺に入れてしまったライターが火葬中に破裂し、火葬炉を破損させたケースも報告されています。
また、ヘアスプレーや制汗スプレーなどの缶製品、携帯電話や携帯ゲーム機に使われるリチウム電池なども同様に危険です。火葬炉の故障や作業員の事故につながりかねないため、爆発の危険物は絶対に棺に入れないようにしましょう。
なお、心臓ペースメーカーを装着していた故人の場合、ペースメーカー本体が高温で破裂する危険があるため火葬前に必ず斎場に申告して取り外してもらう必要があります。
現金・貴重品・金券類:法律で禁止
硬貨は金属製で火葬後に遺骨へ付着しやすく、さらに貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号)が定める「硬貨の損傷行為」に抵触する可能性もあるため、棺に納めるのは避けるのが一般的です。
紙幣は同法の直接対象ではありませんが、燃え残りや灰が遺骨に混ざるおそれがあることから、多くの火葬場が持ち込みを控えるよう案内しています。したがって、故人にどうしてもお金を持たせたい場合でも、本物のお金を棺に入れるのはNGと心得ましょう。
代わりに、六文銭のように紙に印刷した模擬紙幣や燃える素材で作られた擬似貨幣を副葬品とする方法があります。また貴金属の装飾品や宝石類も副葬品にはできません。
燃えないだけでなく、万一火葬中に紛失・消失した場合に遺産トラブルや誤解を生む恐れがあるためです。例えば高価な指輪を棺に入れて焼いてしまうと、「本当に焼いたのか?盗まれたのではないか?」といった疑念が残る場合もあります。
そのため貴重品は基本的に火葬しないのがマナーです。どうしてもという場合は、火葬後に遺骨と共に骨壺に入れることができないか葬儀社と相談する手もあります。いずれにせよ、現金や高価品は棺に入れないのがルールとなっています。
大きすぎる物・大量の紙類:燃え残りや遺骨に影響があるもの
サイズが大きすぎる物や大量の副葬品も避けるべきです。たとえ一つ一つは燃える素材でも、量が多過ぎると火葬炉内で十分に燃焼しきれず燃え残ったり、灰の量が増えて遺骨を覆ってしまったりすることがあります。
具体的には、布団・毛布などの寝具類や大量の衣服、分厚い本やアルバムを何冊もといったケースです。辞書や百科事典などの厚みのある書籍や写真アルバムは紙とはいえ燃えにくく、火葬場で断られることが多いので注意しましょう。
また、極端に大きなぬいぐるみも中綿の量が多いため不完全燃焼を起こしやすく、灰が大量に出て遺骨に付着しやすいためNGとされます。副葬品はあくまで故人とのお別れの象徴ですから、何でもかんでも入れてしまうのではなく、火葬に支障をきたさない範囲で選ぶことが重要です。
入れられない副葬品の把握と対応策
棺に入れてはいけない副葬品は多岐にわたりますが、その多くは「燃えない」「危険」「有害」「量が多すぎる」のいずれかに該当します。
具体的には、金属類・ガラス類・陶器類、スプレー缶や電池などの爆発物、プラスチックやビニール製品、硬貨・紙幣や貴重品、大型・大量の物などです。これらは火葬炉の故障や遺骨の損傷につながる恐れがあるため禁止されています。
もし遺族にとってどうしても入れてあげたい品が禁止品に該当する場合は、代替方法を考えましょう。例えば「実物は入れずに写真だけ棺に入れる」「火葬後に骨壺へ入れることを検討する」「形見分けとして手元に置く」などの対応策があります。
大切な人を送り出す最後の場面ですから、ルールを守りつつ創意工夫で想いを伝えることができると理想的です。
地域・宗教で異なる副葬品の習慣と工夫

副葬品に関するルールや習慣は、地域の慣習や宗教の違いによっても異なる場合があります。また各市町村の火葬場ごとに細かな持ち込み規定が設けられており、同じ品でも地域によって扱いが変わることもあります。
本章では、代表的な宗教的副葬品の例や地域ごとの違いを紹介し、さらにどうしても入れたい品が入れられない場合の対処法について解説します。公的機関が公開しているガイドラインも参考にしながら、地域・宗教に配慮した副葬品の選択と工夫を見ていきましょう。
六文銭を入れる伝統と現代の対応
日本の仏教葬儀には、故人があの世へ旅立つ際に三途の川の渡し賃としてお金を持たせる習慣があります。その代表が六文銭(ろくもんせん)と呼ばれる冥銭です。
六文銭とは江戸時代以前の古い通貨(一文銭)6枚分のことで、亡き人が極楽浄土までの道中で困らないようにとの願いを込めて棺に納める伝統儀礼でした。現在でも仏式葬儀の副葬品として六文銭はメジャーな存在であり、公営斎場でも死装束の頭陀袋(ずだぶくろ)の中に六文銭を入れる習慣が続いています。
実際の硬貨を棺に入れることは現代ではできないため、紙に六文銭の絵柄を印刷したものや木製の六文銭模型が用いられています。
自治体が運営する斎場でも、実物の古銭ではなく燃えやすい紙製または木製の六文銭を組み込んだ白装束セットを備品として用意している例があります。
例えば、大阪府高槻市の「市営葬儀式場のしおり」では、仏式の葬儀備品として「六文銭入り頭陀袋」を含む白装束一式を提供すると明記されています。長野市松代斎場の公式ページでも、販売する「かたびら一式」に六文銭が含まれると案内されています。
どうしても故人に「六文銭」を持たせてあげたい場合は、棺ではなく火葬後に遺骨と共に骨壺へ納める方法も検討されています。実際、法律上も問題のない火葬後であれば硬貨類を骨壺に一緒に入れて墓所に納めること自体は禁止されていません。
六文銭に限らず、お守りや経本など宗教的な副葬品については宗派の慣習と火葬場の規則を両立させる形で工夫することが大切です。宗教的意義の深い品ほど、現代のルールに即した代用品や方法で故人に持たせてあげましょう。
地域によって異なる火葬場のルール
日本各地の火葬場には、それぞれ独自のルールやマナーがあります。他地域では問題なくても、ある地域の斎場では持ち込み禁止とされている品も存在します。
たとえば、沖縄県南部広域市町村圏事務組合「いなんせ斎苑」の公式資料では、副葬品の例として「ぬいぐるみ」「CDなど化学繊維製品」を禁止品目に挙げています。また、愛知県知立市が公開する注意文書でも「大きなぬいぐるみ」「CD」などが入れてはいけない副葬品として明記されています。
これは、地域の火葬炉設備や過去のトラブル事例に基づいて決められていることが多く、可燃物であっても炉に負荷をかけるものは事前に排除しているのです。
そのため、他県から実家に帰って葬儀を行う場合などは特に注意が必要です。習慣の違いだけでなく、自治体ごとの細かな規定を確認しなければ「地元では入れたのにこちらでは入れられない」という事態も起こりえます。
島根県出雲市など、公営斎場の公式サイトなどで持ち込み禁止品の一覧を公開しているところもありますので、事前に目を通しておくと安心です。不明な点は遠慮なく葬儀社や斎場に問い合わせ、地域のルールに沿った副葬品選びを心がけましょう。
入れられない品は写真・代替品の活用を
故人や遺族が「どうしてもこれだけは入れてあげたい」と思う品に限って、ルール上NGということも少なくありません。そのような場合でも、副葬品として気持ちを届ける工夫はできます。
まず有効なのが、写真に残して代わりに入れる方法です。実物は棺に納めず、品物の写真や画像をプリントして故人に持たせることで、「形見」を一緒に入れてあげたのと近い意味合いを持たせることができます。例えば愛用のギターや車など大型で入らないものは、その写真を縮小プリントして副葬品とするケースがあります。
次に、火葬後に遺骨と共に収める方法も検討しましょう。棺に入れて火葬できない金属製の指輪やアクセサリーなどは、収骨の際に遺骨と一緒に骨壺に入れることを許可してくれる場合があります。
これなら火葬炉を傷める心配もなく、最終的に故人と同じお墓に納めることができます。ただし斎場によって対応が異なるため、事前に相談が必要です。
また、形見分けとして他の親族に託すことも一つの方法です。棺に入れられなかった品は大切に保管し、葬儀後の法要やメモリアルコーナーで飾るなど、別の形で故人を偲ぶことに活かせます。
「棺に入れる」以外の形で気持ちを表現する選択肢もあることを覚えておきましょう。
専門家への相談で最善の見送りに
副葬品について疑問があれば、葬儀社のスタッフや火葬場の職員に相談するのが一番です。各地域の細かな規定や実務に精通したスタッフなら、副葬品の判断に迷ったときにも心強い味方となってくれます。
たとえば大手葬儀社の「よりそうお葬式![]() 」には全国対応の相談窓口があるため、副葬品や葬儀プランについて電話一本で確認できます。葬儀で不安がある場合は、遠慮せずに相談しましょう。
」には全国対応の相談窓口があるため、副葬品や葬儀プランについて電話一本で確認できます。葬儀で不安がある場合は、遠慮せずに相談しましょう。
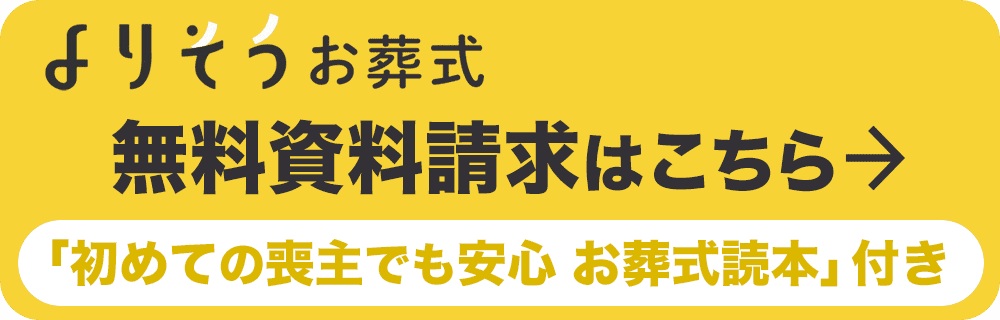
葬儀社によっては、六文銭の代用品や燃える素材で作られた副葬品セット(紙製の人形や思い出グッズなど)を用意してくれるところもあります。遠慮せず希望を伝え、プロの視点で安全かつ遺族の気持ちが叶う方法を一緒に考えてもらいましょう。
公営斎場でも「副葬品は必要最小限に」とお願いしている所が多いように、基本は入れすぎず控えめにが原則です。
しかし最終的には故人と遺族の心が大事ですから、どうしても譲れないものがあるなら専門家と相談しつつ折り合いをつけましょう。しっかり準備と確認を行えば、ルールを守りながらも心残りのない見送りができるはずです。
ルールと想いを両立した副葬品選び
地域や宗教によって副葬品の習慣や規制には違いがありますが、最も優先すべきは火葬場が定めるルールであることに変わりはありません。伝統的な六文銭なども、現代では紙や木の代用品を使うなど安全面に配慮した形で受け継がれています。
もし入れたい物が入れられない場合でも、写真を納めたり骨壺に収めることを検討するなど、想いを伝えるための代替策があります。
大切なのは事前に確認と準備を行い、ルールと故人への想いを両立させることです。副葬品選びで悩んだ際は専門家に相談しながら進めることで、安心して故人を送り出すことができるでしょう。
心に残るお別れのために

副葬品は故人への最後の贈り物です。何を棺に納めるか考える時間は、同時に故人との思い出を振り返る大切なひとときでもあります。安全に火葬を行うためのルールを守りつつ、心からの想いを込めた品を選ぶことで、悔いのないお別れにつながるでしょう。
地域の決まりや宗教の習慣に配慮しながらも、最も大事なのは故人と遺族の気持ちです。適切な副葬品を通じて、故人への感謝と愛情を胸に、穏やかな旅立ちを見送りましょう。
最後に、副葬品について不安な点があれば専門家に相談し、納得のいくかたちで送り出してあげてください。
参考リンク
・財務省『財務省 FAQ「硬貨に穴を開けても良いですか」』
・デジタル庁 法令検索「e-GOV」貨幣損傷等取締法
・大阪府高槻市「市営葬儀式場のしおり」
・長野市松代斎場
・沖縄県南部広域市町村圏事務組合「いなんせ斎苑」
・愛知県知立市「副葬品における制限項目について」
・島根県出雲市「斎場」副葬品の注意事項