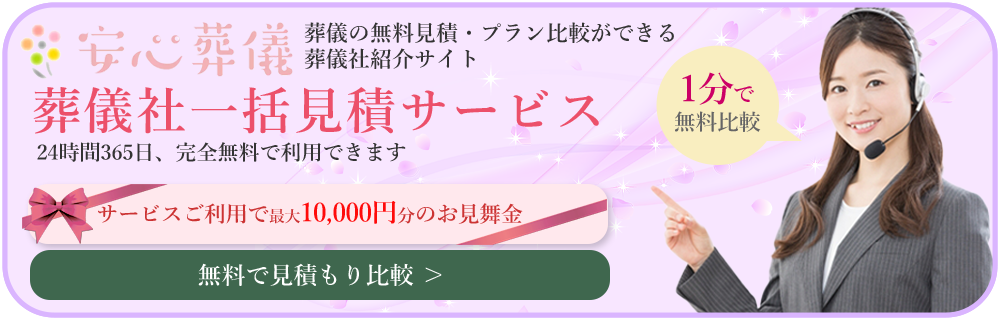直葬(火葬式)は、通夜や告別式を行わず、火葬だけで見送るシンプルな形です。費用や準備の負担を抑えられる一方で、従来の葬儀を当然と考える家族や菩提寺の理解を得るには工夫が必要です。
この記事では、生前に自分の葬儀を直葬にしたいと考えている人が、家族にどう伝えれば納得してもらえるか、そして亡くなったあとの段取りをどう準備すればよいかを整理します。
後日の法要や親族への説明まで視野に入れ、安心して希望を実現するための具体的な方法を解説します。
目次
直葬の基本を押さえておく

直葬は通夜や告別式を省き、火葬だけで見送る方法です。一般的な葬儀とは流れが大きく異なり、準備や費用、家族への伝え方まで考え方を変える必要があります。
どこを省いてよいか、どこは必ず残すべきかを知っておけば迷いが減ります。後日の法要や菩提寺への相談も含め、最初に基礎を共有しておくことが、納得感のある選択につながります。
直葬の流れと準備のポイント
直葬は短い流れで進むため、限られた時間をどう使うか、どこに備えるかを家族で共有しておくことが大切です。
次の点を確認しておくと、慌ただしさを減らし落ち着いた見送りにつながります。
- 流れの把握
安置 → 納棺 → 出棺 → 火葬 → 収骨が基本の順序。通夜や告別式がないため、火葬炉前が唯一のお別れの場になります。 - 別れの工夫
時間が数分〜十数分と短いため、献花や手紙を納める順番を決めておくと落ち着いて臨めます。 - 僧侶の対応
読経は必須ではなく、当日依頼するか、四十九日など後日の法要で重きを置くかを選べます。 - 安置期間の確認
法律上、死亡後24時間は火葬できないため、ドライアイスや施設利用料など安置費用を見積もっておく必要があります。 - 役割分担
搬送や役所手続きは省けないため、届出担当や葬儀社との窓口をあらかじめ割り振ると混乱を防げます。
こうした準備を前もって整えるだけで、直葬は「急ぎ足で終わる葬儀」ではなく、短くても気持ちを込めた時間に変えることができます。
 費用を抑えて故人を送る最もシンプルな葬儀ー直葬の流れと注意点
費用を抑えて故人を送る最もシンプルな葬儀ー直葬の流れと注意点
菩提寺への相談と向き合い方
菩提寺がある家庭では、直葬という形に戸惑いが出やすいものです。特に長年のお付き合いがある場合、「通夜や告別式を省くのは失礼ではないか」と感じる住職もいます。
そのため、できるだけ早い段階で事情を説明し、理解を得られるようにしておくことが大切です。相談するときは「省く部分」と「残す部分」をはっきり伝えると受け入れてもらいやすくなります。たとえば、
- 火葬当日に炉前で読経をお願いする
- 四十九日や納骨、一周忌など後日の法要を丁寧に営む
といった工夫を示せば、「供養を軽んじているわけではない」と伝わります。寺院ごとに謝礼や連絡の手順が異なるため、前もって確認しておくと当日の迷いも減ります。
一方で、菩提寺と疎遠な家庭では葬儀社を通じて僧侶を紹介してもらうことも可能です。たとえば「小さなお葬式」が提供する僧侶手配サービス「てらくる」なら、読経や法要の依頼を安心して任せられます。
こうしたサービスを利用する場合も、後日の法要はどこで行うか決めておくと無理のない形で供養を続けられます。宗教観や家族の事情を尊重しながら、何を省いて何を残すか話し合うことが、親族間の不安を和らげる近道です。
直葬が増えてきた理由

ここ十数年で、家族だけで見送る小規模な葬儀が増え、直葬を選ぶ人も確実に広がっています。その背景にはいくつかの要因があります。
- 高齢化と核家族化によって、参列する親族が少なくなった
- 介護や医療の費用負担が重く、葬儀の支出を押さえたい家庭が増えた
- コロナ禍で大人数の葬儀を控える意識が広がった
都市部では直葬を受け入れられやすい一方で、地域の結び付きが強い地方では「従来の葬儀こそふさわしい」という意見も根強く残っています。
数字や流行だけに左右されず、自分の家庭の事情や親族の顔ぶれを基準に考えることが大切です。直葬に抵抗がある場合でも、後日の法要や偲ぶ会を組み合わせれば、心残りを和らげられると感じる人も多くいます。
形式よりも「どう気持ちを込めるか」が重視される時代に変わりつつあります。
直葬にかかる費用の内訳
直葬は会場費や接待費が不要なため、総額を抑えやすい傾向があります。
ただし火葬料や安置料、搬送費、棺や骨壺などの費用は別途必要です。葬儀社によってプランに含まれる範囲が違うため、見積書での確認が欠かせません。
特に確認したい項目は次の通りです。
- 病院から自宅や安置所までの搬送費
- 安置施設の利用料やドライアイス代
- 火葬場の使用料(別途実費のことが多い)
- 棺や骨壺などの基本物品
- 僧侶への謝礼や後日の法要費用
「安さ」だけで判断せず、サポート体制や追加料金の有無も含めて確認しましょう。
その際には、一括見積サービスを利用すると便利です。たとえば「安心葬儀」なら、複数社の見積もりをまとめて取り寄せられるため、条件を揃えて比較しやすくなります。
相見積もりを取ったあとは、条件や日付などを記録に残しておくと後で見直す際に役立ちます。
家族で共有したい基本のポイント
あらかじめ当日の段取りや役割分担を決めておくと、落ち着いて進められます。菩提寺がある場合は、早めに相談して理解を得ておくと安心です。
追加費用を見落とすと負担が増えることがあるため、見積書の確認は欠かせません。数字よりも家族の納得を大切にし、情報を共有しておくことが、直葬を選ぶうえで重要なポイントになります。
家族に理解してもらうための伝え方

直葬を望む気持ちは、生前のうちに家族へしっかり伝えておくことが大切です。
亡くなった後では本人の意思を確認できず、遺族が戸惑ったり反対意見で揺れたりすることもあります。特に直葬は従来の葬儀の形と異なるため、周囲の理解を得るには丁寧な説明が欠かせません。
ここでは、自分がなぜ直葬を選びたいのかを整理し、家族に伝える方法を紹介します。言葉だけでなく書面でも残す工夫や、菩提寺への相談の仕方も含め、生前にできる準備を具体的に見ていきます。
直葬を選びたい理由を整理する
直葬を望む気持ちは、心の中で考えているだけでは家族に伝わりません。生前のうちに言葉や文字にして残すことが大切です。
エンディングノートなどに、「費用を抑えたい」「高齢の配偶者に負担をかけたくない」「参列者が限られるので大きな式は必要ない」など、理由を具体的に書き出してみましょう。抽象的な価値観よりも、誰のどんな負担を減らせるのかを示す方が説得力があります。
理由は一つに絞らず、主な理由と補足的な理由を順に示すと納得してもらいやすくなります。また、一般的な葬儀と比べて何を省き、何を残すのかをはっきり伝えると誤解を避けられます。
最後に「法要や納骨は後日にきちんと行う」と付け加えれば、直葬でも大切に見送るつもりでいることが家族に伝わります。
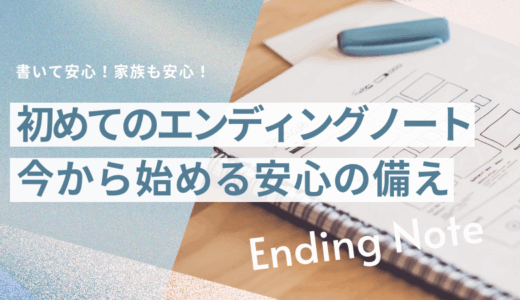 はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
誰にどう伝えるか工夫する
直葬を望む気持ちは、生前のうちに家族や近しい親族へ伝えておくことが大切です。特に反対が予想される人には、早い段階で個別に説明しておくと話が進めやすくなります。誰にどの順番で話すのかを決めておけば、余計な行き違いを防げます。
一方で、亡くなった後に訃報として伝える場合は、内容を端的にまとめておく必要があります。直葬の場合、従来の葬儀と違う点をはっきり知らせることが重要です。
- 通夜と葬儀は行わない
- 火葬のみで見送る
- 後日に集まる場を設ける予定がある
呼ぶ人と呼ばない人の基準は家族で共有し、不公平感が残らないようにします。また、当日の連絡窓口を一人に決め、問い合わせや変更を集約すると負担が軽くなります。
直葬の希望を書面に残す
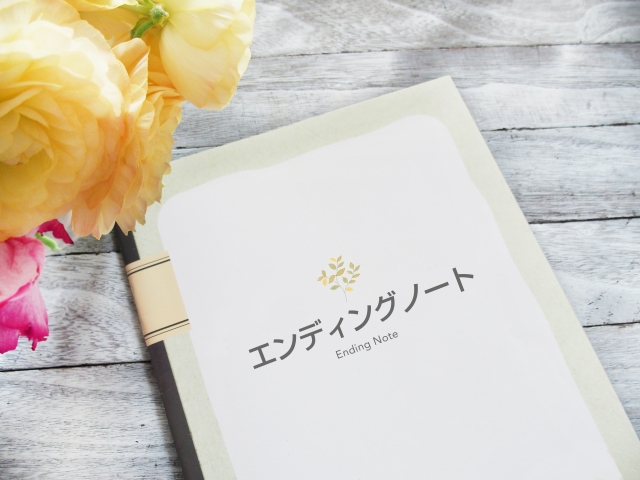
口頭でのお願いは時間が経つと忘れられたり、解釈がずれたりすることがあります。確実に伝えるために、エンディングノートや遺言などに直葬の希望を書き残しておきましょう。
理由・呼ぶ範囲・当日に依頼したいこと・後日の法要の方針などを具体的に記しておくと、家族が判断しやすくなります。あわせて、緊急連絡先や依頼する葬儀社の名前、プラン名、連絡方法まで記載すると安心です。
文書は家族の代表者と共有し、保管場所も伝えておけば安心です。更新日を入れておくと「古い情報ではないか」という不安もなくなります。誕生日や季節の区切りなどに合わせて見直す習慣を持つと続けやすいです。
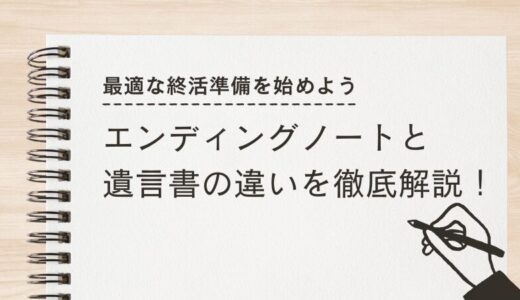 エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
菩提寺への説明と相談
菩提寺がある場合は、直葬を望む理由と後日の法要を丁寧に行う考えを伝えると理解が得やすくなります。
寺院によって対応は異なり、火葬当日に読経をしてもらえる場合もあれば、四十九日や納骨を重視するところもあります。事前に確認しておけば、家族が判断に迷わずに準備を進められます。
あわせてお布施の考え方や連絡の順序も整理しておくと安心です。もし菩提寺が遠方にある場合は、近隣の寺院に依頼したり、葬儀社から紹介を受けたりする方法もあります。
話し合いの経過は家族とも共有し、誰がいつ連絡したのかを記録に残しておくと、後の行き違いを避けやすくなります。
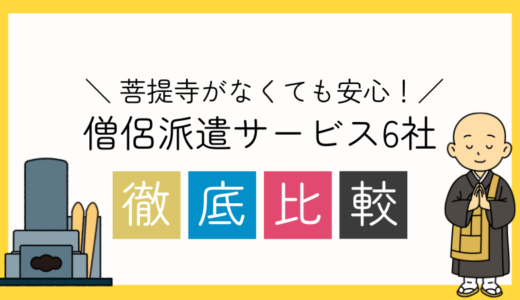 非公開: 菩提寺がなくても安心!僧侶派遣サービス6社徹底比較
非公開: 菩提寺がなくても安心!僧侶派遣サービス6社徹底比較
家族が納得しやすい進め方
家族に直葬を理解してもらうには、理由をはっきり伝えること、情報を具体的に示すこと、手順を見通しやすくしておくことが大切です。生前に準備を重ねておけば、話し合いもスムーズになります。
- 理由を言葉にする
主な理由と補足的な理由を整理し、費用や負担の具体例を添えて説明する - 伝え方を工夫する
書面と口頭の両方で共有し、反対意見には代案を示しながら応じる - 連絡の整理
訃報の伝え方や招く範囲をあらかじめ決め、家族で共有しておく - 寺院との相談
法要の形や日程を事前に話し合い、記録を残しておく
ここまでを整えておけば、当日の混乱や後悔を減らせます。直葬は従来の葬儀と違うからこそ、準備と説明が家族の理解を深める力になります。
直葬に必要な手続きを整理する
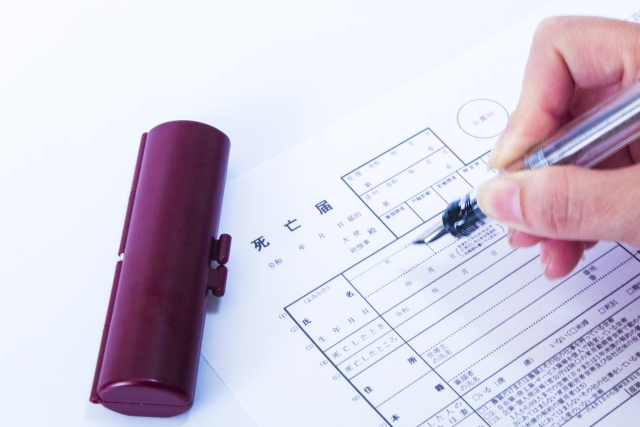
直葬を選ぶ場合も、死亡直後には避けられない手続きがあります。
直葬は一般的な葬儀とは流れが違い、通夜や告別式を省く分、火葬の準備や役所の届け出がより早く求められることが多いです。死亡診断書の提出から火葬場の予約、安置施設の利用まで、手続きの一つひとつが直葬の段取りに直結します。
ここでは、直葬に特有の注意点に絞り、必要な流れを整理していきます。
死亡診断書と火葬許可証
直葬を行うには、まず医師から発行される死亡診断書(または死体検案書)が必要です。この書類は役所に死亡届を出す際に添付し、火葬許可証を受け取るための必須資料となります。
直葬では通夜や葬儀を挟まないため、火葬の日程を早めに決める必要があり、死亡診断書の準備が遅れると手続き全体が滞ってしまいます。
市区町村役場に死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。この許可証は火葬当日に火葬場へ持参しなければならず、忘れると火葬ができません。死亡届の提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」ですが、直葬では日程調整が短期間で進むため、できる限り早く届け出るのが望ましいです。
葬儀社に依頼すれば代行してくれる場合もありますが、直葬を希望する場合はあらかじめ誰が手続きを担うのかを家族で決めておくと安心です。
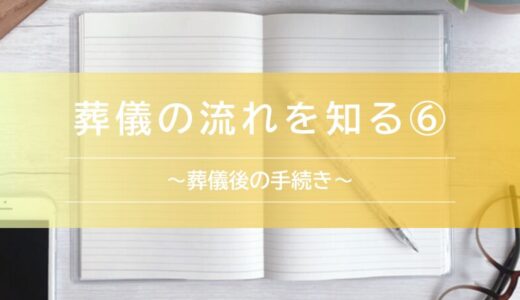 葬儀の流れを知る⑥〜葬儀後の手続き〜
葬儀の流れを知る⑥〜葬儀後の手続き〜
火葬場の予約
直葬では通夜や告別式を行わないため、火葬の日時をすぐに決める必要があります。
都市部では火葬場が混み合い、数日待つことも珍しくありません。火葬の日程が決まらないと安置の延長や追加費用が発生するため、早めの予約が欠かせません。
通常は葬儀社が役所や火葬場に連絡して調整してくれますが、自分で手続きする場合は死亡届を出す前に仮予約を求める自治体もあるので注意が必要です。特に「友引」の翌日などは希望が集中しやすく、第一希望が取れないこともあります。複数候補日を準備しておくと日程が組みやすくなります。
また、火葬料は住民かどうかで差が出る場合があります。居住地以外の火葬場を利用すると追加費用がかかることもあるため、自治体ごとの規定を事前に確認しておきましょう。
火葬当日の流れ
直葬では、納棺・出棺から火葬、収骨までが一日の中で進みます。通夜や告別式を行わないため、火葬炉前での数分から十数分ほどの短い時間が、事実上の「お別れの場」となります。
当日は、棺に花や手紙、故人の愛用品を入れる時間を設けると、限られた中でも気持ちを込めやすくなります。僧侶の読経を希望する場合は火葬場に同行してもらうこともでき、簡素ながらも区切りをつける雰囲気を整えられます。
火葬が終わると収骨が行われ、遺族が順に箸で遺骨を拾い、骨壺に納めます。ここまでを終えると一連の直葬は完了となりますが、その後の四十九日や納骨式をきちんと行うことで、儀式を省いた分を補うことができます。
直葬では「時間が短い」ことが大きな特徴になるため、あらかじめ家族で段取りや心構えを共有しておくと落ち着いて臨めます。
直葬に必要な手続き
ここまで紹介した流れを一覧にすると、次のようになります。手続きの順番や注意点をあらかじめ把握しておけば、慌ただしい中でも落ち着いて進められます。
| 手続き | 直葬でのポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 死亡診断書 火葬許可証 |
火葬に必須の書類。最初に整える必要がある | 書類が遅れると火葬日程を決められない |
| 安置と搬送 | 通夜を省くため、火葬までの間に安置が必要 | 安置料やドライアイス代が追加になることがある |
| 火葬場の予約 | 火葬日時を早く決める必要がある | 混雑期は希望日に取れないことがある |
| 火葬当日の流れ | 炉前での短い時間が唯一のお別れの場となる | 献花や手紙などで心を込める工夫が大切 |
一覧にすると流れはシンプルですが、実際は火葬場の混雑状況などによって判断が求められます。特に火葬場の予約や安置の手配は地域差が大きく、費用や日程に直結します。生前のうちに確認しておけば、家族が迷わずに進められるでしょう。
こうした手続きを支えてくれるのが、信頼できる葬儀社です。どの葬儀社を選ぶかが直葬をスムーズに進めるカギとなります。
葬儀社を選ぶときの考え方

火葬場の予約は、葬儀社を通じて行うのが一般的です。直葬は儀式を省く分、手続きや火葬の段取りを支える葬儀社の力が大きくものを言います。
ここでは、直葬に対応できる葬儀社を選ぶときのポイントと、火葬場の予約で知っておきたい注意点を紹介します。事前に比較・相談しておけば、いざというときに落ち着いて進められるでしょう。
直葬プランがあるかどうか
葬儀社によっては、直葬プランを設けていない場合があります。通夜や告別式を前提とした一般葬のみを扱うところもあるため、まずは直葬に対応できるかどうかを確認することが第一歩です。
プランがある葬儀社なら、搬送から安置、火葬までの流れがひとまとめになっており、必要な段取りをスムーズに進められます。
また、直葬の取り扱い実績が豊富な会社は、火葬場や役所とのやり取りに慣れているため、全体の流れを落ち着いて進めやすい傾向があります。公式サイトやパンフレットで直葬の扱いを明示している会社を選ぶと、検討がしやすくなります。
料金と内容をしっかり確認する
直葬は一般葬に比べて費用を抑えやすいとされますが、料金に含まれるサービス内容は葬儀社ごとに大きく異なります。
搬送や安置にかかる費用が含まれているか、火葬料は別途必要か、棺や骨壺がどの程度の仕様かなどを必ず確認しましょう。安く見えても「安置料は別」「霊柩車は追加」といったケースもあり、総額が想定より高くなることがあります。
以下は見積もりで確認したい代表的な項目です。
| 項目 | プランに含まれるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 搬送費 (病院→安置) |
含む場合と別料金の場合あり | 深夜や距離超過で追加料金になることもある |
| 安置料 ドライアイス |
多くは別料金 | 安置日数が延びると費用がかさむ |
| 火葬料 | プラン外のことが多い | 居住地外利用は割増になるケースも |
| 棺・骨壺 | シンプルな仕様が基本 | グレード変更で追加料金が発生する |
| 僧侶への謝礼 | 原則含まれない | 依頼する場合は別途準備が必要 |
確認の際は、見積書と照らし合わせながら不足や不明点を質問しましょう。複数社の見積もりを同じ条件で比較すれば金額の違いが明確になり、安心して判断できます。
料金の安さだけにとらわれず、当日のサポート体制や事後相談まで含めて検討することが大切です。
 直葬のすべてがわかる!費用から地域別の相場まで詳しく解説
直葬のすべてがわかる!費用から地域別の相場まで詳しく解説
いつでも相談できる体制かどうか

人の死は時間を選ばず訪れるため、直葬を希望する場合でも葬儀社が24時間365日対応しているかは重要な確認点です。
深夜や早朝に亡くなった場合、すぐに搬送や安置の手配ができるかどうかで家族の負担は大きく変わります。電話がすぐにつながり、担当者が落ち着いて対応してくれるかを事前に確かめておくと安心です。
また、遠方での急な逝去や転勤・施設入所などで住まいと死亡地が離れることもあります。そうした場合に備え、全国に提携先を持つ葬儀社や、地域ネットワークが整った葬儀社を選ぶと手配がスムーズです。
大手サービスであれば、こうした体制が整っていることが多いです。例えば「小さなお葬式」は、24時間365日全国対応のサポート体制を整えており、どの地域でも安心して相談できます。
自分たちの生活圏や状況に合った体制かどうか、しっかりと確認をしましょう。
火葬場の予約の注意点
直葬は通夜や告別式を行わない分、火葬の予約が準備の要になります。
都市部では火葬場が混み合い、数日待たなければならないことも珍しくありません。希望日に予約が取れないと安置日数が延び、費用や遺族の負担が増えるため、早めの手配が欠かせません。
通常は葬儀社が役所や火葬場に連絡して予約を調整しますが、自治体によっては死亡届の提出前に「仮予約」を受け付ける仕組みを設けています。例えば静岡県磐田市、兵庫県三木市、石川県輪島市などでは、死亡届提出前に仮予約を行い、その後に本予約へ切り替える運用がとられています。
最終的には火葬許可証がなければ火葬できないため、必ず役所での手続きを済ませる必要があります。
また「友引」の翌日などは希望が集中しやすく、複数の候補日を考えておくと安心です。火葬料は居住地内と居住地外で差がある場合もあり、他地域の火葬場を利用すると追加費用が発生することもあります。
信頼できる業者をどう見極めるか
直葬はシンプルだからこそ、限られた時間の中で搬送や安置、火葬の手続きを確実に進める必要があります。
料金やプラン内容だけでなく、担当スタッフの姿勢や対応力を見ておくことが重要です。問い合わせの際に丁寧に説明してくれるか、質問に曖昧な返答をせず、きちんと答えてくれるか確認しましょう。
可能であれば事前相談や見積もり依頼のときに、スタッフの接し方や対応の速さを体感しておくと安心です。パンフレットや公式サイトの情報に加え、実際の相談で「任せられる」と思えるかどうかが決め手になります。
直葬のあとに考えたい供養の形

直葬は式を省くことで負担を抑えられますが、その分お別れの時間が短く、心残りを抱える人も少なくありません。遺族や親族の気持ちに配慮し、後日の供養や集まる場をどう設けるかを考えておくことが大切です。
ここでは、直葬後に行える法要や偲ぶ会の形、遺族が感じやすい後悔や戸惑いへの対処、周囲への説明の工夫を整理します。シンプルな見送りであっても、心の区切りと供養の機会をきちんと確保すれば、落ち着いてお別れを受け止められます。
火葬前にできるお別れの工夫
直葬では通夜や告別式がないため、火葬炉前でのお別れが数分程度になることもあります。その短さに戸惑う遺族も少なくありません。そこで、限られた時間を心に残るものにするために、小さな工夫を取り入れると安心です。
例えば、棺に花や手紙、故人の愛用品を納める準備をしておくと、慌ただしい中でも気持ちを込めて送り出せます。火葬炉に納める前に一人ずつ言葉をかけたり、全員で献花をしたりするだけでも、心の整理につながります。
希望があれば僧侶に読経をお願いし、簡単なお別れ式として時間を持つことも可能です。
大がかりな儀式がなくても、こうした工夫によって「しっかり見送れた」という実感が残りやすくなり、後悔を和らげる助けになります。
誰に参列してもらうかを決める
直葬は基本的に近親者のみで行うことが多いですが、特に親しかった人には立ち会ってもらいたいと考える場合もあります。友人や長年の同僚など、故人との関係が深い人が少人数でも加われば、お別れの場が温かいものになります。
ただし呼ぶ範囲を限定すると、知らせを受けなかった人が後で不満を抱くこともあるため注意が必要です。
呼ぶ人と呼ばない人の線引きをする場合は、その理由を家族の中で共有し、事前に説明できるようにしておくと安心です。全員を呼ばない代わりに、後日改めて偲ぶ会や法要に声をかける方法もあります。
後日に行える供養の形

直葬は火葬で完結するため、従来の通夜や告別式に代わる供養の場を後日に設けることが大切です。
代表的なのは四十九日や一周忌といった仏教行事で、僧侶を招いて法要を営むことで区切りをつけられます。これらは故人の冥福を祈るだけでなく、遺族や親族が再び集まって思い出を語り合う機会にもなります。
形式にこだわらなければ、自宅で写真や遺品を囲みながら親しい人だけで集まる会を開いたり、オンラインで遠方の親族とつながって思い出を共有する方法もあります。近年は「お別れの会」や「偲ぶ会」として自由な形式を選ぶ人も増えています。
直葬を選んだからといって供養の場が失われるわけではありません。後日の法要や集まり方を工夫することで、故人をしのぶ気持ちは十分に伝えられます。
 四十九日法要とは?意味・流れ・準備やマナーをわかりやすく解説
四十九日法要とは?意味・流れ・準備やマナーをわかりやすく解説
周囲への説明と理解を得るために
直葬はまだ一般的な葬儀と比べると理解が進んでいないため、親族や友人から疑問や不満の声が出ることがあります。特に高齢の親族の中には「なぜ通夜や告別式をしなかったのか」と戸惑う人も少なくありません。
そうしたときには、故人の強い希望だったことや、遺族の負担を減らすための選択だったことを丁寧に伝えることが大切です。説明するときに意識したいのは次の点です。
- 故人の希望を明確に伝える
「本人が望んだ形である」ということを軸にする - 遺族の負担軽減を理由として添える
経済面や体力面の事情を説明する - 感謝の言葉を欠かさない
「ご理解いただけるとありがたいです」と添える - 別の機会を案内する
後日の法要や偲ぶ会に招待する
直葬そのものに理解が及ばなくても「故人を大切に思う気持ちは同じ」という姿勢を共有すれば、多くの場合は受け入れてもらえます。
直葬後に心残りを減らすために
直葬は短い時間で見送る分、後日の法要や集まりをどう持つかが大切になります。火葬前の小さなお別れを丁寧にし、参列してもらう人の範囲を事前に決め、後日の供養を準備しておけば、遺族も落ち着いて受け止めやすくなります。
周囲には故人の希望や遺族の考えを説明し、理解を求める姿勢を持つことで誤解を減らせます。直葬はシンプルな形だからこそ、気持ちを補う工夫が必要です。
直葬を選んだ人の体験談から学ぶ

実際に直葬を望んだ人の体験を知ることで、準備や家族の気持ちの動きを具体的にイメージできます。
ここでは生前から直葬を望んでいた2つのケースを紹介し、どのように準備を進め、家族がどう受け止めたのかを見ていきます。
Aさん(80代女性)のケース
Aさんは夫に先立たれ、娘と二人暮らしをしていました。
早くから「自分の葬儀は直葬で十分」と繰り返し伝え、エンディングノートにも書き残していました。理由は「高齢の親族に負担をかけたくない」「残したお金は娘の生活に役立ててほしい」という思いからでした。
娘のBさんは最初こそ戸惑いましたが、母の考えを尊重しようと話し合いを重ねました。二人で複数の葬儀社を調べ、直葬プランを事前に契約しておいたため、亡くなったときの手続きはスムーズでした。
火葬当日は娘夫婦と孫たちだけが参列し、棺に花や手紙を入れて静かに見送りました。式典や読経は省きましたが、短い時間でも穏やかに別れを告げられました。
その後、親族や知人には「故人の希望により直葬で見送りました」と伝え、四十九日法要と納骨は菩提寺で営みました。高齢の姉妹からは「少し寂しい気もする」との声もありましたが、最終的には「その人らしい見送りだった」と受け入れられました。
Bさんは後に「母の希望を叶えられたことで安心できた。準備をしていたから落ち着いて進められた」と振り返っています。
Cさん(70代男性)のケース
Cさんは「できるだけ簡素にしてほしい」と直葬を希望し、妻と二人で準備を進めていました。しかし、親族の中には「告別式もなしでは故人に失礼だ」と強く反対する人がいました。特に年配の兄が納得せず、話し合いは一時平行線をたどりました。
その際、妻がCさんのエンディングノートを見せ、「本人が何度も口にしていた希望であること」を伝えました。さらに「火葬だけにする代わりに、四十九日には必ず法要を営む」と補足したことで、兄も渋々ながら理解を示しました。
当日は近親者のみで火葬を行い、参列できなかった親族には後日法要と食事会を設けて改めて報告しました。結果として「思ったより落ち着いた形で見送れた」「故人の意志を尊重できたのは良かった」という声に変わりました。
Cさんの家族は「事前に希望を文章で残してくれたことが助けになった」と振り返っています。反対意見が出たときこそ、故人の意思を示す材料や、後日の供養の具体案を用意しておくことが有効だと実感したそうです。
体験談から見える学び
2つの事例からわかるのは、直葬を希望しても準備の有無や周囲への説明の仕方で結果が大きく変わるということです。
生前から希望を明確に残し、家族と話し合っておけば、当日は落ち着いて進められます。また、反対する親族がいたとしても、故人の意思を示す書面や後日の供養の提案があれば歩み寄れる余地が生まれます。
直葬は簡素な形式だからこそ、事前の準備と説明が重要です。希望を形に残し、家族と共有しておくことが、摩擦を減らしながら本人の思いを実現する近道になります。
直葬を選ぶときに大切にしたいこと

直葬は費用や準備の負担を抑えられる一方で、従来の葬儀とは異なるため家族や親族の理解が欠かせません。事前に理由を整理して伝えること、書面に残して共有すること、寺院や関係者への相談を早めに行うことが、安心して進める基盤になります。
火葬前の限られた時間をどう大切にするか、誰に参列してもらうか、後日の供養をどう設けるかを考えておくと、心残りを減らせます。実際の体験談でも、希望を明確にし準備を整えた家庭ほど落ち着いて見送ることができていました。
直葬を検討している人にとって大切なのは、形式を省くことそのものではなく、「どうすれば本人の希望と家族の安心の両方を満たせるか」という視点です。
理由を言葉にする、エンディングノートに残す、家族と話し合う——こうした小さな準備を始めるだけでも、いざというときの不安を大きく減らすことができます。