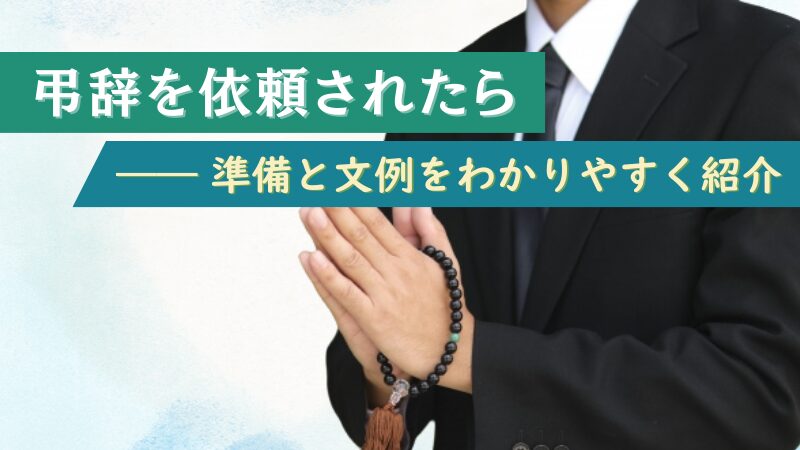弔辞は、故人との思い出を語り、その人柄を参列者に伝える大切な役割です。
依頼されたときは誰でも緊張しますが、難しく考える必要はありません。自分の言葉で心に残っている出来事を語ることが、何よりも大切です。短い時間でも準備の手順を押さえれば、落ち着いて式に臨むことができます。
この記事では、弔辞を準備するときの流れや話の組み立て方、安心して本番を迎えるための工夫をわかりやすく解説します。
弔辞の依頼を受けたときに確認したいこと

弔辞をお願いされるのは、故人とのご縁を信頼されている証です。
限られた時間の中で準備するためには、まず必要な情報を把握しておくことが大切です。葬儀の形式や進行、弔辞の位置づけを早めに確認すれば、準備に迷うことなく落ち着いて進められます。
ここでは、依頼を受けた直後に確認しておきたいポイントをまとめました。
故人との関係と役割を意識する
弔辞の内容は、依頼を受けた人の立場や故人との関係性によって変わります。
親しい友人として選ばれたなら日常のエピソードを中心に、職場を代表して依頼されたなら業務での姿を交えて伝えるのが自然です。まずは「なぜ自分がお願いされたのか」を意識すると、弔辞の方向性が見えやすくなります。
形式ばった言葉よりも、自分だからこそ語れる体験を取り上げることが、心に残る弔辞につながります。
式の形式と持ち時間を確認する
弔辞は葬儀の進行に組み込まれているため、式の形式や持ち時間を把握しておくことが欠かせません。
仏式や無宗教式など、式の形によって雰囲気や話す人数、順番も変わります。一般的には3分程度が目安ですが、念のため喪主に確認するのが安心です。事前に条件を把握しておけば、原稿の長さや構成を無理なく整えられ、落ち着いて準備を進めることができます。
話す内容の方向性を決める
弔辞を引き受けたら、まずどのような場面を取り上げるかを整理してみましょう。
大きな功績を語るよりも、日常の中で感じた人柄や気遣いを描く方が、参列者の心に届きやすくなります。故人の人物像をどう伝えるかを意識しながら、思い出をいくつか書き出してみましょう。
話したいエピソードを決めると、その後の構成づくりも迷わずに進められます。最初の段階で方向性を決めておくことが、短期間の準備を効率的に整えるポイントになります。
依頼を受けたときの心構え
弔辞を依頼されることは、大きな信頼を寄せられている証です。自分に務まるかどうかを過度に気にする必要はありません。大切なのは、故人を思う気持ちを素直に言葉に表すこと。
文章の完成度よりも、誠実さが伝わるかどうかが何より大事です。受け止める姿勢を持ち前向きに準備を進めれば、自然と式にふさわしい言葉へとまとまっていくでしょう。
自分らしい表現で語ることを意識すれば、それが安心して弔辞を務めるための支えとなります。
弔辞を準備するときの基本ステップ

弔辞を引き受けたら、限られた時間で効率よく準備することが大切です。無理に長くしなくても構いません。故人を思い出すエピソードを整理し、シンプルな構成にまとめれば、落ち着いて式に臨めます。
ここでは弔辞を準備する流れと、安心して式に立つための工夫を紹介します。
故人を思い出すエピソードを選ぶ
弔辞は立派な経歴よりも、日常の中での人柄を伝える方が心に響きます。まずは思い出をいくつか書き出してみましょう。
たとえば以下のように整理すると、弔辞のイメージがはっきりしてきます。
- 家族や友人との会話で印象に残ったこと
- 仕事や地域活動での姿勢やふるまい
- 趣味や日常の小さな習慣
内容は一場面につき一つのメッセージに絞り、参列者にも共感してもらえる形にすると自然です。誇張する必要はなく、実際に感じた人柄をそのまま伝えることが、温かい弔辞につながります。
 著名人による感動的な弔辞6選 | 松井秀喜が長嶋茂雄に送った弔辞など
著名人による感動的な弔辞6選 | 松井秀喜が長嶋茂雄に送った弔辞など
話の流れを自然にまとめる方法
弔辞は時間が限られているため、話の流れをシンプルに整えることが大切です。
基本は「挨拶→故人の紹介→エピソード→感謝と別れの言葉」という流れにまとめると、聞き手が迷わずに受け止められます。
| 各ステップ | 内容のポイント |
|---|---|
| 挨拶 | 式に参列できたことへの感謝を述べる |
| 故人紹介 | 人柄を一言で表す |
| エピソード | 具体的な場面を一つ紹介する |
| 結び | 感謝と別れの言葉で静かに締める |
この流れに沿えば、自然にまとまり、時間内に収めやすくなります。
時間内に収めるためのポイント
弔辞は一般的に2〜3分程度が目安とされます。早口になると内容が伝わりにくく、逆に長すぎると式全体に影響します。
そこで、原稿を声に出して読む練習をし、実際にかかる時間を計ってみましょう。句読点のところで軽く息を整える印をつけると、読みやすさが増します。さらに、進行が押したときに備えて「短縮版」を用意しておくと安心です。
通常の原稿と短縮版を二つ準備しておけば、どのような状況でも柔軟に対応でき、落ち着いて本番を迎えられます。
準備を支えるちょっとした工夫
原稿は大きめの文字で印刷し、行間を広めに取ると読みやすくなります。眼鏡を使う方は当日も忘れずに持参し、照明が暗い会場では懐中電灯付きのペンを用意すると安心です。
練習は全文を繰り返す必要はなく、冒頭と結びの部分を重点的に読むだけでも十分効果があります。準備の目的は完璧に暗記することではなく、気持ちを落ち着けて言葉を届けることにあります。
ちょっとした工夫を重ねていけば、本番の緊張も自然と和らぎ、式にふさわしい弔辞を落ち着いて話せるでしょう。
弔辞を安心して語るために

弔辞は準備した原稿を人前で語る大切な場面です。多くの人が緊張しますが、基本の姿勢やちょっとした工夫を意識すれば落ち着いて話すことができます。
ここでは、声の出し方や感情の整え方、言葉選びなど、本番で役立つポイントをまとめました。
緊張をやわらげる呼吸と声の使い方
人前に立つと緊張で声がうわずることがあります。そんなときは、話し始める前に一度深く息を吐き、ゆっくり吸うだけで落ち着きが戻ってきます。
声は無理に大きくする必要はなく、普段より少し低めのトーンで話すと安定感が出ます。マイクがある場合は距離を一定に保ち、語尾を強めに言い切ると聞き取りやすさが増します。
緊張するのは自然なこと。呼吸と声のコントロールをしながら進めれば十分です。
気持ちが込み上げたときの対処法
故人を思い浮かべると、感情があふれて言葉が続かなくなることもあります。その場合は無理に話し続けず、数秒間黙って深呼吸をして構いません。会場も静かに待ってくれるので、焦らず気持ちを整えればよいのです。
どうしても言葉が出ないときは用意した原稿を目で追い、一文を読むと流れを取り戻せます。感情を押し殺す必要はなく、自然ににじむ涙や声の震えも弔辞の一部です。正直な姿が参列者の共感を呼び、かえって心に残る言葉になります。
聞き手に届きやすい言葉の選び方
弔辞は難しい表現を使う必要はありません。むしろわかりやすい表現の方が、参列者にまっすぐ伝わります。
長い敬語や比喩を重ねるより、実際の出来事や具体的な行動をそのまま語ると人柄が伝わりやすくなります。たとえば「優しい方でした」と言うより「困っている人に必ず声をかけていた姿が印象に残っています」と具体化すると、聞き手に映像が浮かびます。
飾り立てた言葉よりも、事実をもとにした表現が何よりの誠実さを生みます。大切なのは、伝える相手の耳にすっと届く言葉を選ぶことです。
本番で意識しておきたいこと
弔辞は完璧さよりも誠実さが大切です。本番では次の3点を意識すると、落ち着いて聞いてもらえる内容になります。
- ゆっくり
早口にならないよう、句読点ごとにひと呼吸置く - はっきり
明瞭な声で、語尾まで丁寧に伝える - 短めに
必要以上に長くせず、要点を押さえて話す
冒頭で参列者を見渡し、あとは原稿に視線を戻して進めれば十分です。途中で言い間違えても、落ち着いて言い直せば問題はありません。終わりの言葉は一拍置いてから語ると、余韻が残り会場全体に静けさが広がっていきます。
とはいえ、それでも準備や式の進行に不安を感じる方は多くいます。そのようなときは、事前に葬儀社スタッフに相談しておくと安心です。
たとえば大手葬儀社の「小さなお葬式」では、弔辞の準備や式の流れに関する不安にも丁寧に対応してくれます。実績のある専門スタッフがサポートしてくれるため、葬儀当日も心強い支えとなるでしょう。
弔辞をどうしても引き受けられない場合

弔辞は基本的に引き受けるのが望ましいですが、体調ややむを得ない事情によって務められないこともあります。そのような場合でも、故人や遺族への敬意を大切にしながら、別の形で想いを示すことができます。
ここでは、弔辞を担当できないときに考えられる対応方法を紹介します。
体調の問題で務められないとき
病気や持病の悪化、長時間の離席が難しいなど、体調面の理由で弔辞を務められないことがあります。その際は、できるだけ早めに事情を伝えることが大切です。「体調の都合で弔辞を務めるのは難しいのですが、別の形でお手伝いさせていただきたい」と添えると、誠意が伝わります。
無理をして途中で中断してしまうよりも、できない理由を明確に伝える方が、結果的に式の進行に迷惑をかけません。誠実な説明と、他にできることを示す姿勢が安心につながります。
感情があふれて言葉にできないとき
故人との関わりが深いほど、感情が込み上げて弔辞を務めることが難しくなる場合があります。
そのときは「故人への思いが強すぎて言葉にできません」と正直に伝えるのも一つの方法です。代わりに別の親族や友人に原稿を託し、代読してもらえば、気持ちはしっかり届けられます。
自分の代わりに誰かが読んでくれることで参列者にも思いが伝わり、弔辞としての役割も果たされます。無理に立とうとせず、信頼できる人に任せることも誠実な判断です。
別の形で思いを伝える方法
弔辞を担当できない場合でも、弔電や供花、受付や会場案内など、別の形で式に関わることができます。「弔辞は務められませんが、弔電で気持ちをお伝えします」といった言葉を添えれば、誠意が十分に伝わります。
弔電を送る場合は、「VERY CARD」のようなオンラインで弔電を手配できるサービスがおすすめです。VERY CARDの場合、1,000種類以上の文例が使用でき、デザインも豊富なので故人の雰囲気に合った弔電を届けられます。
大事なのは「弔辞ができない=関わらない」ではなく、自分なりの方法で故人や遺族に敬意を表すことです。
弔辞を引き受けられないときは、誠実に事情を伝えたうえで代読や別の提案をすれば、遺族も安心して準備を進められます。
大切なのは、故人を敬い遺族に配慮する姿勢です。自分が置かれた状況を踏まえつつ、誠実な方法で関わることを意識しましょう。
立場ごとの弔辞文例

弔辞は語る人の立場によって、内容や言葉の選び方が変わります。親しい友人として語るのか、職場を代表して伝えるのか、あるいは親族として思いを述べるのか——それぞれにふさわしい表現があります。
ここでは、立場ごとの弔辞の具体例を紹介します。
親しい友人としての弔辞例
本日は、故人〇〇さんのご冥福を心よりお祈りいたします。
〇〇さんとは学生時代から長い時間を共に過ごしました。いつも周囲に気を配り、友人の小さな変化にもすぐに気付いて声をかけてくれる人でした。特に忘れられないのは、私が大きな失敗をして落ち込んでいたとき、黙って隣に座り、最後に『また頑張ればいいさ』と笑ってくれたことです。その言葉にどれほど救われたか、今でも鮮明に覚えています。
その優しさは私だけでなく、多くの仲間に届いていました。〇〇さんが残してくれた温かさを胸に、これからも歩んでまいります。〇〇さん、本当にありがとうございました。どうか安らかにお休みください。
友人の弔辞では、特別な功績よりも「日常の姿」を描くことが心に残ります。具体的なエピソードを入れることで、言葉に説得力が増します。
職場を代表しての弔辞例
〇〇株式会社を代表し、謹んで哀悼の意を表します。
〇〇さんは常に誠実に業務へ向き合い、同僚を励まし、周囲に安心を与えてくださいました。締め切りが迫る中でも落ち着いた対応で職場をまとめ、時には後輩を優しく支える姿が印象に残っています。そうした姿から私たちは、働くことの意味や人を思いやる心を学びました。
〇〇さんと共に過ごした日々の記憶は、私たちにとって大きな財産です。これからもその姿勢を忘れず、社員一同、日々の業務に励んでまいります。心より感謝を申し上げ、〇〇さんのご冥福をお祈りいたします。
職場を代表する弔辞では、個人的な思い出よりも「周囲に与えた影響」「会社全体に残した功績」に焦点を当てるのが自然です。肩書や立場を明確に示すと、公的な場に調和した弔辞になります。
親族としての弔辞例
遺族を代表して、故人〇〇への思いを述べさせていただきます。
〇〇はいつも家族を大切にし、どんなに忙しい日々の中でも必ず笑顔を向けてくれる人でした。食卓を囲みながら交わした何気ない会話や、休日に一緒に散歩した時間は、今も鮮やかに心に残っています。思い出の一つひとつが家族にとってかけがえのない宝物です。
これからも私たちは〇〇を思い、その温かさを胸に過ごしていきます。〇〇、本当にありがとう。どうか安らかに眠ってください。
親族の弔辞では、家庭の中での姿が語られることが特徴です。大げさな言葉よりも、食卓や日常の一場面など身近なエピソードを入れることで、参列者に温かな雰囲気が伝わります。代読をお願いする場合でも、原稿は自分の思いを込めて用意することが大切です。
心に届く弔辞にするために
紹介した弔辞は、あくまで一つの形にすぎません。大切なのは、故人との体験や気持ちを自分の言葉で重ねることです。実際に声に出してみて、自然に話せる表現に直していけば、それだけで自分らしい弔辞になります。
形式を整えることよりも、故人を思う心が素直に伝わるかが一番のポイントです。文例を手がかりに、自分なりの言葉を少しずつ加えていくことで、参列者の心に届く弔辞へと仕上がります。
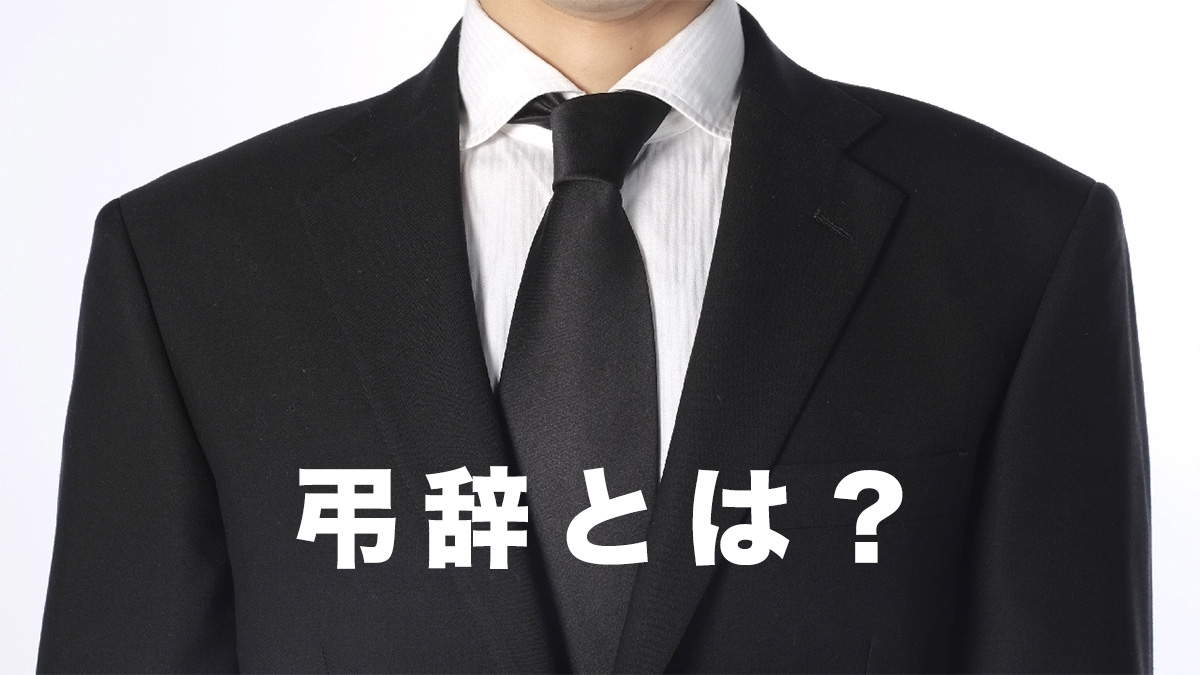 豊富な文例でわかる!弔辞の例文集と書き方・読み方
豊富な文例でわかる!弔辞の例文集と書き方・読み方
弔辞を通じて伝えられること

弔辞は特別なことではなく、故人を思う気持ちを言葉にするものです。長さや表現の華やかさよりも、心を込めて伝えることが何より大切です。参列者にとっても、飾らない言葉の中にこそ故人の姿が浮かび上がり、共に偲ぶ時間が深まります。
故人との思い出を整理し、落ち着いて語ることを意識すれば、それだけで十分に役目を果たせます。たとえ声が震えたり、涙で言葉が途切れたとしても、それは弔辞の一部として自然に受け止められるでしょう。
大切なのは、故人との思い出を参列者と分かち合うことです。その時間が、遺族や参列者にとって心を支える力となります。弔辞を頼まれたときには、自分だからこそ語れる思いを素直に伝え、故人への感謝と敬意を伝えてください。