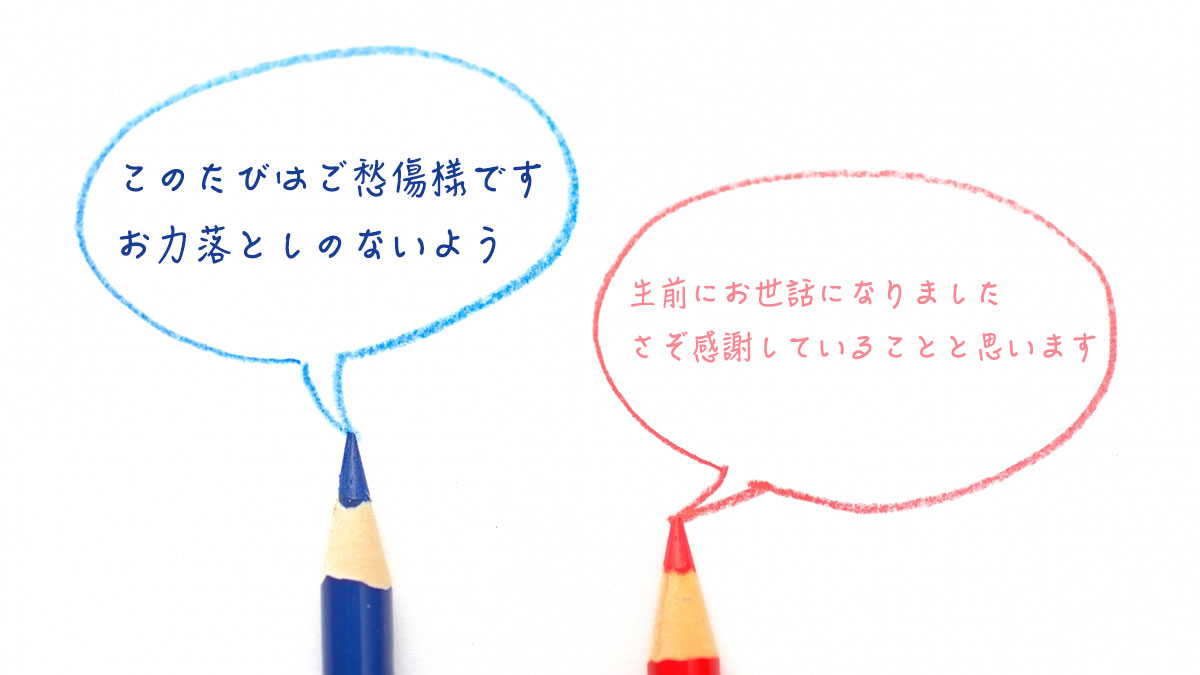お悔やみの言葉とは、故人の死を悼み、遺族を慰め励ますためにかける弔慰のメッセージです。突然の訃報を受けてお通夜や葬儀に参列するとき、多くの人は何と声をかければよいか言葉に迷うものではないでしょうか。この記事では、一般の弔問客として恥ずかしくないお悔やみの基本マナーや避けるべき表現を解説し、職場関係や友人知人へのケース別に使えるお悔やみの例文を豊富に紹介します。メールやLINEでお悔やみを伝える場合の書き方や、仏教・神道・キリスト教など宗教別の配慮についても触れています。分かりやすくまとめていますので、いざという時の参考にしてください。
目次
お悔やみの言葉とは?基本的な役割とポイント
お悔やみの言葉とは、故人の死を悲しみ遺族の心情に寄り添って慰めるための挨拶です。通夜や葬儀の場では長々と話すことはせず、ごく短い挨拶で気持ちを端的に伝えるのが基本です。大切なのは、故人の死を悼む言葉と遺族をいたわり励ます言葉の二つのポイントを押さえることです。
例えば「突然の訃報に接し驚いています。(故人様のお名前)のお人柄を偲び、心よりお悔やみ申し上げます」のように、驚きや悲しみといった自分の気持ちを伝えつつ、相手を気遣う言葉を組み合わせるとよいでしょう。
遺族側(喪主やご遺族)も、お悔やみの言葉をかけられた際には感謝の気持ちを込めて簡潔にお礼を返します。弔問側・遺族側いずれにとっても、相手を思いやる気持ちをシンプルな言葉で表現することが何より大切です。堅苦しく考えすぎず、あなたなりの誠意が伝わる一言を心がけましょう。
「お悔やみ申し上げます」の意味と使い方

「お悔やみ申し上げます」は、お葬式や弔電などで頻繁に使われる弔意表現です。「悔やむ」という言葉に尊敬を表す「お」と謙譲の「申し上げる」を付けた丁寧語で、「悲しい気持ちでいっぱいです」という哀悼の意を伝える定型表現にあたります。たとえば「心からお悔やみ申し上げます」「謹んでお悔やみ申し上げます」といった形で用いられ、ビジネスから親しい間柄まで幅広く使える便利なフレーズです。改まった手紙やメールの文面でも結びの言葉としてよく使われます。
「お悔やみ申し上げます」に似た表現としては、「心よりお悔やみ申し上げます」「謹んで哀悼の意を表します」「謹んでお悔やみ申し上げます」などがあります。よりカジュアルな会話では「ご愁傷様です」と声をかけることもあります。「ご愁傷様です」は漢字で書くと「ご愁傷様」で、「このたびはご愁傷様でございます」のように改まった場面でも使えますが、親しい友人に対してであれば「ご愁傷様」「本当に残念だったね」のように少しくだけた調子で伝える場合もあります。いずれにせよ、直接会って伝える場合でもメール等でも、最後は「お悔やみ申し上げます」で結ぶと気持ちが引き締まり、丁寧な印象になります。
お悔やみの基本マナーと避けるべきタブー表現

お悔やみの言葉を伝える際にはマナーにも注意が必要です。悲しみやショックで動揺している遺族に対し、言葉選びを誤るとかえって失礼になってしまうこともあります。以下に、一般参列者がお悔やみを述べる際に避けるべきポイントや表現をまとめました。慌てず落ち着いて行動し、相手の心情に寄り添った言動を心がけましょう。
長話や詮索はしない
弔問の場で遺族を長時間引き留めたり、故人の死因・経緯を詳しく尋ねたりするのはマナー違反です。遺族は様々な対応に追われ忙しいため、挨拶は手短にし、詮索は絶対に避けましょう。お悔やみはあくまで「悲しいです」「おつらいでしょうね」という気持ちを伝えることに留めます。
忌み言葉に注意
葬儀の席では不吉なイメージを連想させる言葉(忌み言葉)を避けます。「重ね重ね」「度々」「ますます」など不幸の繰り返しを連想させる重ね言葉は使用しません。「続く」「再び」などの言葉も同様です。また「死亡」「死去」「生きていた頃」など生死を直接的に表す言葉も避け、「ご逝去」「ご生前」といった婉曲表現に言い換えるのがマナーです。さらに「浮かばれない」「落ちる」などの不吉な言葉もNGとされています。会話だけでなく弔電や手紙の文面でも使わないよう十分に注意しましょう。
前向きすぎる発言を控える
励まそうとするあまり「元気を出して」「頑張って」などの前向きすぎる言葉をすぐにかけるのは逆効果になることがあります。深い悲しみに暮れる遺族にとって、一般的な励ましの言葉ですら心に響かないばかりか負担に感じる場合があります。まずは悲しみに共感し寄り添う姿勢を示すことが大切です。相手の気持ちに余裕が出てきたと感じられるまでは、いたずらに励ましすぎないようにしましょう。
これらのマナーを押さえ、「何と声をかけるべきか…」と迷ったときはシンプルで無難な一言で構いません。「心よりお悔やみ申し上げます」だけでも気持ちは十分伝わります。大切なのは形式よりも心がこもっていることです。
お悔やみメールを送る場合の件名と書き方

遠方に住んでいる場合や急な訃報に駆け付けられない場合、メールでお悔やみを伝えることもあります。親しい仲であればLINEなどでメッセージを送るケースも増えていますが、目上の方や正式な相手には本来はお悔やみ状(手紙)を出すのが丁寧です。どうしてもメールで連絡する必要があるときは、できるだけ礼を尽くした書き方を心掛けましょう。
まず件名にはひと目で弔電・弔意のメールと分かるようにシンプルに書きます。たとえば件名を「お悔やみ申し上げます(◯◯様 ご逝去に際して)」のようにすると、開封前に弔事の要件だと理解してもらえます。「◯◯様ご逝去のお知らせ」といった件名は、訃報を知らせる立場の人が使う表現なので、弔問側がお悔やみを伝えるメールの件名としては避けましょう。あくまでこちらからの弔意を示すメールであることが分かる表現が望ましいです。
メール本文の書き出しは、通常のビジネスメールなどとは異なり時候の挨拶などは不要です。いきなり本題に入り、「◯◯様のご訃報に接し、驚いております。◯◯様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。」といった形で弔意とお悔やみの言葉を述べます。差し出し人がすぐ分かるよう、自分の氏名も文頭に名乗りとして入れておくと良いでしょう(特に取引先や仕事関係の場合)。文末は「取り急ぎ書中にてお悔やみ申し上げます。」などで結び、最後に自分の氏名・連絡先を記載します。
お悔やみメールの例:件名「お悔やみ申し上げます」
突然のご連絡にて失礼いたします。△△様(故人様のお名前)のご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご生前に賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに、ご遺族の皆様のお悲しみはいかばかりかと拝察申し上げます。本来であればすぐにでも弔問に伺うべきところですが、メールにて恐縮ではございますがお悔やみ申し上げます。まずは書中にてお悔やみ申し上げます。
山田太郎(自分の氏名)
ビジネス関係のお悔やみメールでは上記のようにやや改まった言い回しを用います。一方、友人知人へのメールやメッセージであればもう少しくだけた表現でも構いません。「急な知らせで本当に驚きました。心からお悔やみ申し上げます。」など、あまり難しい敬語にせずとも気持ちは伝わります。ただし、絵文字や顔文字は絶対に使わないようにしましょう。メールを送った後、可能であれば電話や手紙で改めて連絡したり、落ち着いた頃にお伺いしたりすると、より誠意が伝わります。
LINE・SNSでお悔やみを伝える場合の注意点
近年ではSNSで訃報を知ることもあり、LINEやFacebookのメッセージ機能などでお悔やみを伝えるケースもあります。親しい間柄であれば迅速に気持ちを伝えられるメリットがありますが、デリケートな内容だけに注意も必要です。公の場(タイムラインやコメント欄)で突然お悔やみメッセージを書き込むのは避け, プライベートなダイレクトメッセージ(DM)やLINEの個別トークを用いるのが原則です。相手がSNS上で公表していない場合は、SNSで連絡すること自体を控えましょう。噂で聞いて知っただけの場合などは、まずは直接連絡が取れる手段を選ぶ方が無難です。
メッセージの文面はメールよりさらに簡潔で問題ありません。夜分や早朝は避け、相手が落ち着いていそうな時間帯に送りましょう。スタンプや絵文字は用いず、シンプルな文章と言葉遣いで丁寧に気持ちを伝えます。普段はフランクな友人同士でも、このような場面では敬意を込めて「です・ます調」で書くと良いでしょう。
LINEで送るお悔やみメッセージ例文:(友人に宛てたケース)
上記のように、LINEでは改まった敬語表現(です・ます調)を使いつつも、相手へのいたわりや親身な気持ちが伝わる文面にすると良いでしょう。特に親しい仲であれば、「ご愁傷様。本当に残念でなりません」といった少しカジュアルな表現にする場合もあります。しかしどんな場合でも、「w」や顔文字、「泣き」の絵文字などふざけた印象につながる要素は絶対にNGです。文章量は相手の負担にならないよう2~3行程度に収め、長文になりすぎないよう注意します。送信後は相手から返信がなくても焦らず、相手のペースを尊重してそっと見守りましょう。
シーン別:お悔やみの言葉・例文集
ここからは、状況や相手との関係別のお悔やみ例文を紹介します。職場関係や友人知人へのお悔やみ、突然の訃報に接した場合、さらに相手が家族を亡くされたケース(亡くなったのが親御さん・配偶者・お子さん・祖父母それぞれの場合)について、適切な言葉遣いやメッセージ例を具体的に見ていきましょう。自分の立場やシチュエーションに近いものを参考に、状況に合ったアレンジを加えてみてください。大事なのは型通りの文章をそのまま使うのではなく、例文をヒントに自分の言葉で伝えることです。
職場関係者へのお悔やみ例文
仕事関係の方(上司・同僚・部下など)がご不幸に遭われた場合のお悔やみは、できるだけ丁寧で失礼のない表現を心掛けます。特に相手が目上の立場であれば、言葉遣いには一層注意が必要です。以下は職場関係者へのお悔やみの言葉の例です。社内メールやビジネス文書で使える文面も意識しています。
上記の例文では、社内の上司に対してそのご家族(お父様・お母様など)が亡くなったケースを想定しています。「ご尊父様」「ご母堂様」といった呼称は目上の相手のご両親に対して使う丁寧な表現です。「ご逝去」「ご冥福をお祈りします」といった厳粛な言葉遣いを用い、社内の他のメンバーを代表して書く場合は「社員一同」「◯◯部一同」といった団体名も入れると良いでしょう。ビジネスメールの場合は前述の通り件名を工夫し、差出人も明記して送付します。直接会ってお悔やみを述べる際も、基本的には同様の表現を口頭で伝えれば問題ありません。沈痛な面持ちで、ゆっくりはっきりと伝えるようにしましょう。
友人・知人へのお悔やみ例文
親しい友人や知人が身内を亡くされた場合は、形式ばった表現よりも相手の気持ちに寄り添った言葉をかけることが大切です。とはいえ、あまりにくだけすぎると礼を失しますので、基本は丁寧な日本語で思いを伝えます。友人だからこそ伝えられる思い出話や故人への感謝の気持ちなどを添えるのも良いでしょう。以下に友人・知人向けのお悔やみ例文を紹介します。
1つ目の例はごく親しい友人同士の口頭でのやり取りを想定し、少しくだけた口調を交えています。2つ目・3つ目の例は友人のお父様や配偶者が亡くなったケースで、思い出や故人への感謝を述べています。友人・知人の場合、形式にとらわれすぎず相手への思いや自分の感情を素直に織り交ぜると、より心に響くお悔やみになります。たとえば「悲しくて胸が張り裂けそうです」「〇〇さんには生前本当に良くしていただきました」など、あなた自身が感じていることを付け加えるのは効果的です。ただし、あくまで主役は遺族の方ですので、自分の悲しみを強調しすぎないようバランスには注意しましょう。
突然の訃報に対するお悔やみ例文
交通事故や急病などによる突然のご不幸に接した際は、心の準備ができていない分、遺族の悲嘆も計り知れないものがあります。そのような場面では、驚きと深い悲しみを共有しつつ相手を気遣う言葉を伝えることが大切です。急な場合のお悔やみ例文をいくつか挙げます。
予期せぬ別れの場合、弔問客としても「こんな時になんと声をかければいいのだろう…」と戸惑ってしまうかもしれません。上記の例文のように、まずは自分も驚いていることを率直に述べ、次に相手の心痛をお察しする言葉を続けると流れがスムーズです。「言葉もありません」「お気持ち察しいたします」といったフレーズは非常によく使われます。また、急な死であることを強調しすぎると遺族の悲しみを深く抉る可能性もありますので、「なぜこんなことに…」といった混乱や動揺をぶつける言葉は避け、できるだけ穏やかな表現で相手をいたわるようにしましょう。遺族への健康面の気遣い(「どうかご自愛ください」「お身体を大切に」等)も添えると、相手を思う気持ちがより伝わります。
家族を亡くした方へのお悔やみ例文(続柄別)
相手の方が身内(家族)を亡くされたケースでは、亡くなった方との続柄によって適切なお悔やみの言葉が多少変わります。故人に対する敬称や触れるべき話題が異なるためです。ここでは、「相手が親を亡くした場合」、「配偶者を亡くした場合」、「子どもを亡くした場合」、「祖父母を亡くした場合」の4つのケースに分けて、それぞれのポイントと例文を紹介します。
相手が親御さん(父母)を亡くした場合
友人や同僚などがご両親を亡くされたとき、まず亡くなった方の呼び方に注意しましょう。相手の親御さんにあたる故人を指す場合は、たとえばお父さん・お母さんではなく「お父様」「お母様」という敬称を使うのが一般的です。改まった手紙や弔電では「ご尊父様(お父様)」「ご母堂様(お母様)」のようなより丁寧な表現も用いられます。どの表現を使うにせよ、親御さんを失った相手の心情に寄り添い、深い感謝や敬意の気持ちも伝えられると言葉がより温かいものになります。
親を亡くした方へのお悔やみでは、故人である親御さんへの感謝や思い出を述べるのも効果的です。「お父様には○○さんの結婚式でお会いした際に優しく声をかけていただきました」「○○さん思いの素敵なお母様でしたね」といった一言があると、遺族にとって故人の存在が偲ばれて嬉しく感じることがあります。ただし相手との関係性によっては詳しい思い出話まで知らない場合も無理に触れる必要はありません。また、相手がまだ若くして親御さんを亡くされた場合、「まだお若いのにさぞ無念でしょう」などの表現は避け、「お気持ち察します」程度にとどめる方が良いでしょう。悲しみを共有しつつも、今後の生活を案じて「どうかお力落としのないように」と気遣う言葉を付け加えると丁寧です。
相手が配偶者(夫・妻)を亡くした場合
相手の方がご主人や奥様を亡くされた場合のお悔やみでは、長年連れ添ったパートナーを失った孤独や不安に寄り添う言葉を意識します。特に高齢のご夫婦で片方を亡くされたケースでは、「これからひとりになってしまう寂しさ」を思いやる配慮が求められます。例えば以下のような表現があります。
1つ目の例は若い夫婦のケース、2つ目・3つ目は主に年配の夫婦のケースを想定しています。配偶者を亡くした方へのお悔やみでは、「これから先大丈夫だろうか」という遺された相手の心細さに触れるような言葉掛けも有効です。ただし、「お一人になってしまいましたね」など直接的に言うのは禁物ですので、「さぞお寂しいことと存じます」「長年支えてこられた分、お心穴の空く思いかと存じます」など柔らかい表現にしましょう。先の見通しを安易に語ったり、「早く元気になって」など急かしたりするのも避けます。相手の心情を察し、静かに寄り添う姿勢が大切です。必要であれば実際に生活面でのサポートを申し出ることも検討しましょう。
なお、故人と喪主が夫婦関係の場合によく使われる表現として「ご冥福をお祈りします」のほか「どうかお力落としのなきよう」などがあります。これらは寂しさに暮れる相手をいたわる定型句です。逆に「大往生だったから…」などと言及するのは適切ではありません。たとえ高齢で亡くなった場合でも「天寿を全うされましたね(大往生でしたね)」といった表現は遺族側が口にするものであり、弔問側から言うものではないとされていますので注意しましょう。
相手が子ども(お子さん)を亡くした場合
お子さんを亡くされた親御さんに対するお悔やみは、非常に慎重な言葉選びが求められます。幼い子どもを失う悲しみは他の何にも代えがたい深さであり、周囲からの言葉もなかなか届かないかもしれません。そのような中でも、決して一人ではないこと、周囲が支えていくという気持ちを伝えることが大切です。
子どもを亡くしたご両親には、かける言葉が見つからないのが正直なところだと思います。無理に気の利いたことを言おうとせず、上記例文のように「残念でなりません」「言葉もありません」といった率直な気持ちを伝えましょう。その上で、「お子さんは愛されて幸せだったはず」「あなた達は決してひとりじゃない」という趣旨の言葉を付け加えると、直接的ではなくともご両親への支えとなる場合があります。「がんばって」「時間が癒してくれる」などの言葉は避け、悲しみを否定せず寄り添う姿勢を示します。また、小さなお子さんの葬儀では参列者側も気を付けるマナーがあります。たとえば子連れでの参列は控える(会場で遺族が幼い子どもを見ると辛さが増す可能性があるため)といった配慮も必要です。心から相手を思いやる気持ちを行動でも示しましょう。
相手が祖父母を亡くした場合
友人や知人が祖父母を亡くされたケースでは、基本的なマナーは親御さんの場合と似ています。おじいさま、おばあさまに当たる故人を指す場合は「お祖父様」「お祖母様」(または改まった表現なら「ご祖父様」「ご祖母様」)という呼称を使います。高齢の方のご逝去である場合、「天寿を全うされた」といった言葉が頭に浮かぶかもしれませんが、それを弔問側が口にするのは避けましょう。遺族側から「大往生でした」と話されたときにうなずく程度に留め、自分からは触れないのがマナーです。
祖父母を亡くされた方へのお悔やみでは、故人の長寿を称えること自体は問題ありません。ただし、上記のように「もっと長生きしてほしかった」という遺族の無念に寄り添う形で述べると良いでしょう。「◯◯様のご存在はご家族にとって大きな支えだったでしょうから、本当にお気落としのことと存じます」のように、故人が家族にもたらした功績や思い出を敬意をもって触れるのも一つです。いずれの場合も、残された相手のこれからの生活を気遣い「どうぞお力落としのありませんよう」「○○さん、くれぐれもご自愛くださいませ」といった締めの言葉を添えると丁寧です。
宗教による違いとお悔やみの表現

日本のお葬式は仏教式が多数派ですが、故人や遺族の宗教が神道やキリスト教である場合、お悔やみの言葉にも配慮が必要です。それぞれの宗教で死後の考え方や慣習が異なるため、できれば宗教ごとに適した言葉を選ぶと良いでしょう。
仏教の場合
日本の仏教式葬儀では「ご冥福をお祈りします」「ご冥福をお祈り申し上げます」といった表現が広く使われています。「冥福」とは仏教でいう冥土(死後の世界)での幸福を意味し、故人の魂が安らかでありますようにという願いを込めた言葉です。故人やご遺族が仏教徒であれば「ご冥福をお祈りします」は適切なお悔やみの言葉と言えます。また仏教では他にも「ご仏前(ぶつぜん)」「成仏されますよう」など独特の表現がありますが、一般参列者がお悔やみとして述べる場合は「お悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈りします」で十分です。仏教では四十九日までは「ご冥福」ではなく「ご仏前」で香典袋に書くなどの決まりもありますが、口頭の言葉としては深く気にしすぎる必要はありません。
神道の場合
神道の葬儀(神葬祭)では本来「冥福」という概念がありません。神道では人は亡くなると祖霊(みたま)となり、家の守護神になると考えられています。そのため、お悔やみでも「ご冥福をお祈りします」は本来ふさわしくないとされます。代わりに「ご遺族様の平安をお祈りいたします」や「安らかなご永眠をお祈り申し上げます」など、仏教色のない表現に言い換えると良いでしょう。ただ、現代の日本では厳密に宗教によって言葉を分ける人ばかりではありません。故人が熱心な神道信者であった場合などは避けた方が無難ですが、特に断りがなければ一般的な「お悔やみ申し上げます」を使っても大きな問題になることは少ないでしょう。どうしても気になる場合は「〇〇様の御霊(みたま)のご平安をお祈り申し上げます」のように表現する方法もあります。
キリスト教の場合
キリスト教(カトリック・プロテスタント)のお葬式では、「冥福」も仏教的な表現なので本来は用いません。キリスト教では人は亡くなると天国へ召されるという考え方をしますので、「天国で◯◯様が安らかにお眠りになりますようお祈りいたします」などと表現すると良いでしょう。プロテスタントでは葬儀は「昇天式」「記念式典」などと呼ばれ、悲しみよりも故人が天に召されたことを神に感謝する場とも位置づけます。そのためあまり過度に悲嘆的なお悔やみは述べず、「故人様の天国での平安をお祈りします」「ご遺族に神の慰めがありますように」といった宗教色のある言葉を使う場合もあります。ただし、キリスト教の場合もご遺族が特に信仰深いわけでなければ、一般的なお悔やみの言葉(お悔やみ申し上げます等)だけでもマナー違反にはなりません。先方がクリスチャンであると分かっているなら、十字架のついたお悔やみカードを送る、聖書の一節を添えるなどの配慮をするとより丁寧でしょう。
このように、宗教によって理想的なお悔やみの表現は若干異なります。とはいえ日本では宗教を意識せず「ご冥福をお祈りします」と述べる人も多いのが実情です。大切なのは先方の宗教や慣習をできる範囲で尊重しようとする気持ちです。もし可能であれば「キリスト教式の葬儀では香典ではなく御花料を包む」といったマナーまで把握しておくとより安心ですし、それが難しくても「知らずに不適切なことを言ってしまったらどうしよう」と萎縮しすぎないようにしましょう。心からの弔意が伝われば、多少表現が違っていても真意は汲み取ってもらえるものです。
お悔やみの言葉まとめ:大切なのは相手を思う気持ち
お悔やみの言葉やメッセージの文例を多数ご紹介してきましたが、最も大切なのは「相手を気遣う心」と「故人を偲ぶ心」です。形式的に正しい言い回しであることも大事ですが、それ以上にあなた自身の言葉で真心が伝わることが遺族にとって慰めになります。悲しみの渦中にいる相手にかける言葉として正解はなく、どんな言葉も届かないかもしれません。それでも、あなたが相手を大切に思っている気持ちや故人への感謝や敬愛の念が感じられれば、きっと遺族の心にも少しずつ届くはずです。
最後に、シチュエーション別の例文を参考にする際のポイントをまとめます。
-
例文はあくまで一例です。そのまま読むのではなく、自分の言葉で言い換えたり、エピソードを付け加えたりしてみましょう。
-
マナーや宗教上のタブーに配慮しつつも、あまりに萎縮せずシンプルで誠実な表現を心掛けましょう。
-
直接会う場合は短くても構いません。お焼香の際に一言「お悔やみ申し上げます」と伝えるだけでも大丈夫です。無理に話を広げようとせず、相手の様子に合わせて静かに寄り添いましょう。
-
文書やメールでは、口頭よりも多少丁寧な文体を意識します。ただし長文になりすぎないように注意し、忌み言葉や失礼な表現が入っていないか送り出す前に再度確認しましょう。
悲しみの場に寄り添うお悔やみの言葉は、誰にとっても簡単なものではありません。だからこそ日頃からマナーや表現を知っておき、いざという時に少しでも相手の力になれるよう備えておきましょう。この記事が少しでもその助けになれば幸いです。心を込めて故人を偲び、慎んで哀悼の意を表しましょう。
※葬儀に参列できない際の「お悔やみ状の例文」と「礼状の基本」はこちらをご参考ください
 葬儀に参列できない際のお悔やみ状と礼状の基本
葬儀に参列できない際のお悔やみ状と礼状の基本